本ページはプロモーションが含まれています。
目次
「終身保険」おすすめ比較。ここがポイント!
| サービス名 | 終身保険RISE[ライズ] | こだわり終身保険v2 | 一生のお守り | 終身保険 | ネオdeとりお | &LIFE 終身保険(低解約返戻金型) | 終身保険 つづけトク終身 | スーパー終身保険 | かしこく備える終身保険 | バリアブルライフ変額保険(終身型)(無配当) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険料:30代男性・1,000万円・終身 | 12,710円 | 21,090円 | 14,100円 | 14,620円 | 18,940円 | 14,870円 | 19,240円 | 12,700円 | 16,630円 | - |
「終身保険」の選び方
1.解約返戻金を重視するか?保険料の安さを重視するか?
終身保険とは
保障が一生涯続く生命保険のこと
を言います。
命は永遠ではありませんから、いつかは保険金がもらえるため「貯蓄性」がある保険となっています。また、途中で解約しても「解約払戻金」が出る仕組みになっています。※解約した場合は、その後の保障はなくなります。
終身保険には大きく分けて2タイプあり
- 解約払戻金が100%を超えるもの
- 解約払戻金が70%程度に抑えられている反面、保険料が安いもの
です。
老後資金を貯めたいのであれば
- 解約払戻金が100%を超える = 払った保険料よりも戻ってくる解約払戻金が大きい終身保険がおすすめ
途中解約の予定がなく、保険料が安いことを重視するのであれば
- 解約払戻金が70%程度に抑えられている反面、保険料が安いものがおすすめ
となります。
「解約払戻金の多さ」「保険料の安さ」どちらを重視するのか?で選ぶべき終身保険は全く変わってきます。
2.保険料払込期間で選ぶ
終身保険は
- 保険料払込期間
というものがあります。
保障は一生涯でも、保険料の支払いは期限を持つことができるのです。
仕事を辞めた後も、高額な保険料を支払うとなると、老後の生活を圧迫してしまうため、「定年までの保険料支払にしたい」というニーズにもこたえるためです。
保険料払込期間の種類としては
- 終身
- ○歳まで
- ○年間
という選び方があります。
「終身で保険料を払い続けたい」というわけでなければ、保険料払込期間の選択肢が豊富な終身保険を選びましょう。
3.保険料が安い終身保険を選ぶ
保険の条件(保険金額、保険料払込期間、保障)が同じであれば
- 保険料が安ければ安いほど良い
ということになります。
多くの場合、保険の条件がまったく一致するということはないのですが、ほとんど同じであれば、保険料が安い終身保険がおすすめです。
4.解約払戻金が大きい終身保険を選ぶ
解約を前提にしていて、老後資金を貯める「貯蓄の代わりに保険を利用したい」という方の場合は
- 解約払戻金が大きければ大きいほど良い
ということになります。
ただし、解約返戻金は、保険によって、どのタイミングで何%戻ってくるのか?が異なります。
- 30歳に加入して60歳まで払えば、60歳で105%戻る終身保険
- 30歳に加入して60歳まで払えば、70歳で108%戻る終身保険
があれば、前者の方が早い段階でお金を手にすることができるため、老後資金の使い道が広がることになります。
単純に解約払戻金の金額だけでなく、タイミングも重要ということを理解する必要があります。
5.特約で選ぶ
終身保険の基本的な保障は
- 死亡
- 高度障害
ですが、それに加えて特約が付いている、またオプションで付けられる終身保険があります。
- 特定疾病診断保険料免除特約
- 年金移行特約
- 三大疾病保険料払込免除特約
- 終身介護保障特約
- 災害割増特約
- 新傷害特約
- 保険料払込免除特約
- リビング・ニーズ特約
- 区分料率適用特約
など
様々なものがあります。
特約によって、要介護状態や三大疾病になった時に保険料の払い込みが不要になり、同じ保険金が受け取れるタイプの終身保険があります。
特約が手厚い方がカバーできるリスクが広がるのですが、特約が手厚ければ手厚いほど、保険料が高くなってしまうため、バランスを見て、ご自身の必要な保障を見極める必要があります。
「終身保険」のよくある質問
Q.貯蓄性が高い終身保険と保険料が安い終身保険はどちらがおすすめですか?
メリットデメリットがあります。
貯蓄性が高い終身保険であれば
- 現役の間 → 保険として万が一の時、ご家族に当面の生活費を用意できる
- 老後(定年後) → 解約すれば、まとまった資金が手に入る
利息の低い預金で預けるよりは、保険の機能も持ちながら、元本以上にお金が増えるため、貯蓄性の高い終身保険を選ぶ方も少なくありません。
保険料が安い終身保険であれば
途中解約を考えなければ、同じ保険金額であれば、保険料は安ければ安い方がお得です。
一生涯保険に入ることを決めていれば、貯蓄性は不要ですから、保険料の安い終身保険を選ぶべきなのです。

個人的には、貯蓄性の高い終身保険よりも、保険料が安い終身保険を選んで、浮いた分を投資に回して自分で資産を増やす運用の方がおすすめです。
「終身保険」おすすめランキング/編集部

オリックス生命/終身保険RISE[ライズ]

-
- 保険料の安さ
- 5
-
- 保険金額・払込期間などの選択肢の多さ
- 5
-
- 貯蓄性の高さ
- 5
-
- 特約の手厚さ
- 4
-
- サポートの手厚さ
- 3
オリックス生命/終身保険RISE[ライズ]がおすすめの理由
オリックス生命/終身保険RISE[ライズ]がおすすめの理由は「保険料の安さ」「払戻率の高さ」です。
終身保険RISE[ライズ]は、終身保険の中でも業界1位、2位の保険料の安さを誇る終身保険です。その上で、払込期間が終了した後は、いきなり払戻率が100%を超えてくる払戻率の高さもおすすめのポイントです。
また、払込期間の選択肢も豊富で、選択肢の多いメリットがあります。
デメリットは、特約が手薄な点です。
オリックス生命/終身保険RISE[ライズ]の口コミ

マニュライフ生命/こだわり終身保険v2
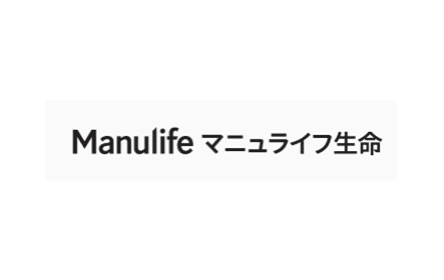
-
- 保険料の安さ
- 3
-
- 保険金額・払込期間などの選択肢の多さ
- 5
-
- 貯蓄性の高さ
- 5
-
- 特約の手厚さ
- 4
-
- サポートの手厚さ
- 4
マニュライフ生命/こだわり終身保険v2がおすすめの理由
マニュライフ生命/こだわり終身保険v2がおすすめの理由は「健康な方は保険料が安くなる」「払戻率の高さ」です。
こだわり終身保険v2は、払込期間が終了した後は、いきなり払戻率が100%を超える払戻率の高さがある終身保険です。
また、タバコを吸わない方は、非喫煙者保険料率(ノンスモーカー料率)が適用されるため、健康な方ほどお得に加入できるメリットがあります。
デメリットは、保険料がやや高い点です。
マニュライフ生命/こだわり終身保険v2の口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:0件

SOMPOひまわり生命/一生のお守り

-
- 保険料の安さ
- 4
-
- 保険金額・払込期間などの選択肢の多さ
- 5
-
- 貯蓄性の高さ
- 4
-
- 特約の手厚さ
- 5
-
- サポートの手厚さ
- 3
SOMPOひまわり生命/一生のお守りがおすすめの理由
SOMPOひまわり生命/一生のお守りがおすすめの理由は「保険料の安さ」「払戻率の高さ」です。
一生のお守りは、終身保険の中でも業界トップクラスの保険料の安さを誇る終身保険です。その上で、払込期間が終了した後は、払戻率が100%を超えてくる払戻率の高さもおすすめのポイントです。
また、三大疾病により所定の事由に該当した場合、以後の保険料のお払込みが必要なくなる特約がついています。
デメリットは、払戻率が100%を超えるけれども、そこまで高いわけではない点です。
SOMPOひまわり生命/一生のお守りの口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:0件

アクサダイレクト生命/終身保険

-
- 保険料の安さ
- 4
-
- 保険金額・払込期間などの選択肢の多さ
- 3
-
- 貯蓄性の高さ
- 3
-
- 特約の手厚さ
- 3
-
- サポートの手厚さ
- 3
アクサダイレクト生命/終身保険がおすすめの理由
アクサダイレクト生命/終身保険がおすすめの理由は「保険料の安さ」です。
アクサダイレクト生命/終身保険は「低解約返戻金型」を採用しているため、保険料が業界トップクラスの安さである点が大きなメリットです。
デメリットとしては、払込期間が終身で、解約返戻金も70%前後と低く抑えられている点です。
アクサダイレクト生命/終身保険の口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:1件
昔からある大手保険会社と違いインターネットでの契約になりますが保険料が安く自分は独身なので最低限の保障で十分なので契約しました。今まで契約していた一般的な大手保険会社と違い契約の中身が分かりやすくシンプルな契約なのも安さの秘密なのかなと思います。解約はするつもりはありませんが、県民共済の様に掛け捨てではないのでお金を無駄にしたという感覚もないのも良いと考えています。契約後も保険の内容に分からないことがあり、ネットで調べただけでは理解できなかったので電話しましたが、担当の方は分かりやすく丁寧に説明してくれたのでとても良かったです。

ネオファースト生命/ネオdeとりお

-
- 保険料の安さ
- 3
-
- 保険金額・払込期間などの選択肢の多さ
- 4
-
- 貯蓄性の高さ
- 3
-
- 特約の手厚さ
- 3
-
- サポートの手厚さ
- 3
ネオファースト生命/ネオdeとりおがおすすめの理由
ネオファースト生命/ネオdeとりおがおすすめの理由は「健康な方は保険料が安くなる」「三大疾病にも備えられる」です。
ネオファースト生命/ネオdeとりおの最大の特徴は、万一のときだけではなく所定のがん・急性心筋梗塞・脳卒中の三大疾病になった時にも、保険金が支払われる点です。医療保険の側面もある終身保険と言えます。
デメリットは、保険料がやや高めの設定で、払戻率も100%を超えない点です。
ネオファースト生命/ネオdeとりおの口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:0件

三井住友海上あいおい生命/&LIFE 終身保険(低解約返戻金型)
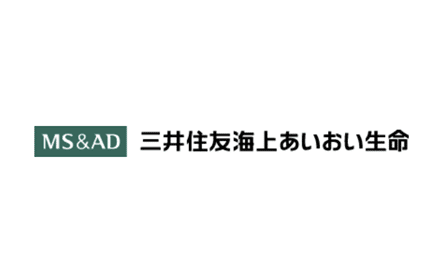
-
- 保険料の安さ
- 4
-
- 保険金額・払込期間などの選択肢の多さ
- 5
-
- 貯蓄性の高さ
- 4
-
- 特約の手厚さ
- 5
-
- サポートの手厚さ
- 4
三井住友海上あいおい生命/&LIFE 終身保険(低解約返戻金型)がおすすめの理由
三井住友海上あいおい生命/&LIFE 終身保険(低解約返戻金型)がおすすめの理由は「保険料の安さ」「払戻率の高さ」です。
&LIFE 終身保険(低解約返戻金型)は、終身保険の中でも業界トップクラスの保険料の安さを誇る終身保険です。その上で、払込期間が終了した後は、払戻率が100%を超えてくる払戻率の高さもおすすめのポイントです。
また、保険料のお払込み満了後は状況に応じて保障内容を変更可能です。死亡保障から、介護年金、年金に切り替えられる自由度があります。
デメリットは、保険金額の上限が1,000万円と低い点です。
三井住友海上あいおい生命/&LIFE 終身保険(低解約返戻金型)の口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:2件
特約の種類が多く、例えばガン家系ならガンの特約をつけたり、認知症家系なら介護保険をつけたりと選択の幅が広い。手続きもそこまで難しくない。が、コロナ禍でコロナではないが給付されるまでに1ヶ月以上かかった。手続きが漏れているのかがわからないので、申請した件の状況がわかるといい。日帰りのちょっとした手術でも保険が下りる。入院手術の際支出を大きく上回る保険が下りて助かった。介護保険として要介護になった場合に月5万円の給付になるが、今後要介護の基準が上がり実際要介護になっても基準に満たずもらえないということにならないか不安を感じる。
「保険の窓口」という店舗で「学資保険」の代わりとしてLIFE終身保険を勧められたので契約しました。子供が大学に入学する年齢で解約すれば掛け金の総額に上乗せして返金されます。私に万が一のことがあった場合に当時医療保険等にも入っていなかったので、学費の用意と何かあった時の両方をカバーできると思い契約しています。「児童手当」の範囲で契約しておりますので、毎月の支払金額に関して気にする事はありません。ただし二人目の時には返金額が下がっていたので、契約する会社選ぶ必要があるとは思います。

メットライフ生命/終身保険 つづけトク終身

-
- 保険料の安さ
- 3
-
- 保険金額・払込期間などの選択肢の多さ
- 4
-
- 貯蓄性の高さ
- 3
-
- 特約の手厚さ
- 3
-
- サポートの手厚さ
- 3
メットライフ生命/終身保険 つづけトク終身がおすすめの理由
メットライフ生命/終身保険 つづけトク終身がおすすめの理由は「年0.60%が最低保証」です。
終身保険 つづけトク終身は、積立利率が、年0.60%で最低保証されているため、保険料払込期間満了後、保障の一部または全部に代えて、その解約返戻金を原資に年金として受取ることができます。(※年金移行特約を付加した場合)
デメリットは、保険料が高い点と保険金額の上限が1,000万円と低い点です。
メットライフ生命/終身保険 つづけトク終身の口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:0件

楽天生命/スーパー終身保険

-
- 保険料の安さ
- 5
-
- 保険金額・払込期間などの選択肢の多さ
- 3
-
- 貯蓄性の高さ
- 3
-
- 特約の手厚さ
- 4
-
- サポートの手厚さ
- 3
楽天生命/スーパー終身保険がおすすめの理由
楽天生命/スーパー終身保険がおすすめの理由は「保険料の安さ」「ポイントが貯まる」です。
スーパー終身保険は「低解約返戻金型」を採用しているため、保険料が1位、2位を争う安さである点が大きなメリットです。さらに楽天ポイントが保険料の1%を毎月獲得できるため、お得に重視した終身保険と言えます。
デメリットとしては、払込期間が終身で、解約返戻金も70%前後と低く抑えられている点です。
楽天生命/スーパー終身保険の口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:1件
申し込みはほとんど項目に回答するだけで行えたので非常にお手軽でしたし、診断結果などを用意する必要がなかったので尚更助かりました。保険料に関しても、年齢に関係なくずっと一律なので、こちらとしても計画性を持ちながら支払いをする事ができていますし、更には元々リーズナブルな料金体系になっているのでランニングコストもかかりにくいです。また、保険に加入する事で楽天ポイントが貰えましたし、サポートのレスポンスも早かったので安心できました。

アフラック/かしこく備える終身保険

-
- 保険料の安さ
- 4
-
- 保険金額・払込期間などの選択肢の多さ
- 3
-
- 貯蓄性の高さ
- 3
-
- 特約の手厚さ
- 5
-
- サポートの手厚さ
- 4
アフラック/かしこく備える終身保険がおすすめの理由
アフラック/かしこく備える終身保険がおすすめの理由は「タバコを吸わない方は保険料が割引」「特約の手厚さ」です。
かしこく備える終身保険は、タバコを吸わない方であれば、保険料が割安になる特約と三大疾病になったら以後の保険料が不要になる「三大疾病保険料払込免除特約」が付いている、特約が手厚い終身保険です。カバーできるリスクが広いメリットがあります。
デメリットとしては、払込期間が終身で、解約返戻金も70%前後と低く抑えられている点です。
アフラック/かしこく備える終身保険の口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:1件
初めて終身保険に入る際に、代理店の方に複数比較(5社以上)して頂いた上で加入を決めました。加入にあたっての月々の保険料もそうですが、60歳を超えた頃からよくなる解約返戻金についても返戻率が高いものを選んだ方が良いとアドバイス頂き、こちらのアフラックの商品に加入する事になりました。特約については特に意識をしておらず、また他の会社も同じような印象であったため、貯蓄に近い感覚で加入を決めました。
私は持病や健康面は特には何も抱えていないのですが、告知も煩雑には感じず、医師の面談や追加資料の提出もなくスムーズに感じられました。

ソニー生命/バリアブルライフ変額保険(終身型)(無配当)

-
- 保険料の安さ
- 3
-
- 保険金額・払込期間などの選択肢の多さ
- 4
-
- 貯蓄性の高さ
- 5
-
- 特約の手厚さ
- 5
-
- サポートの手厚さ
- 4
| サービス名 | バリアブルライフ変額保険(終身型)(無配当) |
|---|---|
| 運営会社 | ソニー生命 |
| 保険料:30代男性・1,000万円・終身 | - |
| 保険料:40代男性・1,000万円・終身 | - |
| 保険料:50代男性・1,000万円・終身 | - |
| 保険料試算条件補足 | - |
| 払戻率 | 運用実績による |
| 払戻率計算条件 | 運用実績による |
| 特約 | 平準定期保険特約 平準定期保険特約(喫煙リスク区分型) 無解約返戻金型平準定期保険特約 家族収入特約 逓減定期保険特約 災害死亡給付特約 傷害特約 がん特約 リビング・ニーズ特約(04) ナーシング・ニーズ特約(04) 保険料払込免除特約(20) 買増権保証特約(92) 5年ごと利差配当付年金支払特約 |
| 保険金額 | 200万円~7億円 ※10万円単位 |
| 払込期間 | 短期払(年数、年齢で選べる) |
| 公式 | 公式サイト |
| 口コミ | 口コミ・評判 |
ソニー生命/バリアブルライフ変額保険(終身型)(無配当)がおすすめの理由
ソニー生命/バリアブルライフ変額保険(終身型)(無配当)がおすすめの理由は「代わりに資産運用してくれる」点です。
バリアブルライフ変額保険(終身型)(無配当)では、資産の運用実績に基づき、死亡・高度障害保険金額が変動(増減)する仕組みになっています。運用実績にかかわらず基本保険金額のお支払いは保証されているため、受け取れる保険金が一定額以上減ることはありません。
つまり、資産運用をソニー生命が代わりにしてくれて、運用結果が良ければ、解約返戻金が増えることを意味します。
デメリットは、資産運用の結果、解約返戻金が減る可能性もあるということです。
ソニー生命/バリアブルライフ変額保険(終身型)(無配当)の口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:0件
「終身保険」おすすめ比較
| サービス名 | 終身保険RISE[ライズ] | こだわり終身保険v2 | 一生のお守り | 終身保険 | ネオdeとりお | &LIFE 終身保険(低解約返戻金型) | 終身保険 つづけトク終身 | スーパー終身保険 | かしこく備える終身保険 | バリアブルライフ変額保険(終身型)(無配当) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運営会社 | オリックス生命 | マニュライフ生命 | SOMPOひまわり生命 | アクサダイレクト生命 | ネオファースト生命 | 三井住友海上あいおい生命 | メットライフ生命 | 楽天生命 | アフラック | ソニー生命 |
| 保険料:30代男性・1,000万円・終身 | 12,710円 | 21,090円 | 14,100円 | 14,620円 | 18,940円 | 14,870円 | 19,240円 | 12,700円 | 16,630円 | - |
| 保険料:40代男性・1,000万円・終身 | 16,530円 | 24,950円 | 18,050円 | 18,870円 | 25,280円 | 18,810円 | 23,680円 | 16,300円 | 21,190円 | - |
| 保険料:50代男性・1,000万円・終身 | 22,570円 | - | 24,250円 | 25,630円 | 35,780円 | 24,990円 | 30,600円 | 22,300円 | 28,530円 | - |
| 保険料試算条件補足 | - | 非喫煙者保険料率 | - | - | 非喫煙者割引 | - | 90歳払済 | - | - | - |
| 払戻率 | 109.9% | 116.0% | 101.2% | 約70% | 96.9% | 101.9% | 約70% | 約70% | 約70% | 運用実績による |
| 払戻率計算条件 | 30歳加入、60歳満期、60歳時点 | 30歳加入、60歳満期、70歳時点、非喫煙者保険料率 | 30歳加入、60歳満期、65歳時点 | 低解約返戻金型 | 30歳加入、60歳満期、60歳時点 | 30歳加入、60歳満期、65歳時点 | 低解約返戻金型 | 低解約返戻金型 | 低解約返戻金型 | 運用実績による |
| 特約 | リビング・ニーズ保険金 介護前払保険金 | リビング・ニーズ保険金 特定疾病保険料払込免除特則 | 特定疾病診断保険料免除特約 年金移行特約 介護一時金特約 介護前払特約 リビング・ニーズ特約 指定代理請求特約 | リビング・ニーズ保険金 | 非喫煙者割引特約 | 終身介護保障特約 災害割増特約 新傷害特約 保険料払込免除特約 リビング・ニーズ特約 区分料率適用特約 | リビング・ニーズ保険金 | リビング・ニーズ保険金 保険料払込免除 | リビング・ニーズ保険金 三大疾病保険料払込免除特約 ノンスモーカー割引特約 災害死亡割増特約 | 平準定期保険特約 平準定期保険特約(喫煙リスク区分型) 無解約返戻金型平準定期保険特約 家族収入特約 逓減定期保険特約 災害死亡給付特約 傷害特約 がん特約 リビング・ニーズ特約(04) ナーシング・ニーズ特約(04) 保険料払込免除特約(20) 買増権保証特約(92) 5年ごと利差配当付年金支払特約 |
| 保険金額 | 200万円~5,000万円 ※100万円単位 | 200万円~7億円 ※10万円単位 | 50万円~ ※10万円単位 | 200万円~4,000万円 ※100万円単位 | 50万円~3,000万円 | 300万円~1,000万円 ※3コース | 200万円~1,000万円 ※4コース | 100万円~5,000万円 ※100万円単位 | 100万円~ ※10万円単位 | 200万円~7億円 ※10万円単位 |
| 払込期間 | 終身払、短期払(年数、年齢で5年ごと) | 終身払、短期払(年数、年齢で選べる) | 終身払、短期払(年齢で選べる) | 終身払 | 60歳、65歳、終身 | 終身払、短期払(年齢で選べる) | 60歳、70歳、90歳 | 終身払 | 終身払 | 短期払(年数、年齢で選べる) |
| 公式 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
| 口コミ | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 |
「終身保険」でおすすめのランキング/利用した方の口コミ・評判
口コミ・評判ランキングは、口コミ件数5件以上で、総合評価順に表示しています。口コミ件数5件未満のものは、口コミ件数が多い順に表示しています。
三井住友海上あいおい生命/&LIFE 終身保険(低解約返戻金型)の評判・口コミ
口コミ総合評価
5.6点
総合評価(10点満点)
最新口コミ 口コミ投稿数:2件
特約の種類が多く、例えばガン家系ならガンの特約をつけたり、認知症家系なら介護保険をつけたりと選択の幅が広い。手続きもそこまで難しくない。が、コロナ禍でコロナではないが給付されるまでに1ヶ月以上かかった。手続きが漏れているのかがわからないので、申請した件の状況がわかるといい。日帰りのちょっとした手術でも保険が下りる。入院手術の際支出を大きく上回る保険が下りて助かった。介護保険として要介護になった場合に月5万円の給付になるが、今後要介護の基準が上がり実際要介護になっても基準に満たずもらえないということにならないか不安を感じる。
「保険の窓口」という店舗で「学資保険」の代わりとしてLIFE終身保険を勧められたので契約しました。子供が大学に入学する年齢で解約すれば掛け金の総額に上乗せして返金されます。私に万が一のことがあった場合に当時医療保険等にも入っていなかったので、学費の用意と何かあった時の両方をカバーできると思い契約しています。「児童手当」の範囲で契約しておりますので、毎月の支払金額に関して気にする事はありません。ただし二人目の時には返金額が下がっていたので、契約する会社選ぶ必要があるとは思います。
楽天生命/スーパー終身保険の評判・口コミ
口コミ総合評価
8.0点
総合評価(10点満点)
最新口コミ 口コミ投稿数:1件
申し込みはほとんど項目に回答するだけで行えたので非常にお手軽でしたし、診断結果などを用意する必要がなかったので尚更助かりました。保険料に関しても、年齢に関係なくずっと一律なので、こちらとしても計画性を持ちながら支払いをする事ができていますし、更には元々リーズナブルな料金体系になっているのでランニングコストもかかりにくいです。また、保険に加入する事で楽天ポイントが貰えましたし、サポートのレスポンスも早かったので安心できました。
アフラック/かしこく備える終身保険の評判・口コミ
口コミ総合評価
7.8点
総合評価(10点満点)
最新口コミ 口コミ投稿数:1件
初めて終身保険に入る際に、代理店の方に複数比較(5社以上)して頂いた上で加入を決めました。加入にあたっての月々の保険料もそうですが、60歳を超えた頃からよくなる解約返戻金についても返戻率が高いものを選んだ方が良いとアドバイス頂き、こちらのアフラックの商品に加入する事になりました。特約については特に意識をしておらず、また他の会社も同じような印象であったため、貯蓄に近い感覚で加入を決めました。
私は持病や健康面は特には何も抱えていないのですが、告知も煩雑には感じず、医師の面談や追加資料の提出もなくスムーズに感じられました。
アクサダイレクト生命/終身保険の評判・口コミ
口コミ総合評価
6.4点
総合評価(10点満点)
最新口コミ 口コミ投稿数:1件
昔からある大手保険会社と違いインターネットでの契約になりますが保険料が安く自分は独身なので最低限の保障で十分なので契約しました。今まで契約していた一般的な大手保険会社と違い契約の中身が分かりやすくシンプルな契約なのも安さの秘密なのかなと思います。解約はするつもりはありませんが、県民共済の様に掛け捨てではないのでお金を無駄にしたという感覚もないのも良いと考えています。契約後も保険の内容に分からないことがあり、ネットで調べただけでは理解できなかったので電話しましたが、担当の方は分かりやすく丁寧に説明してくれたのでとても良かったです。
オリックス生命/終身保険RISE[ライズ]の評判・口コミ
口コミ総合評価
5.4点
総合評価(10点満点)
最新口コミ 口コミ投稿数:1件
本当は加入する予定はなかったのですが、保険の代理店の方に勧められて加入することにしました。月々の保険料は高めなのですが、解約した時に払い戻し金があることと貯蓄性があるということで掛け捨てではない安心感があり決めました。それと通院している状態だったので保険に入れるか心配していたのですが、オリックス生命なら入れる可能性があると保険の代理店の方に言われて申し込んだところ審査も無事に通ったので助かっています。

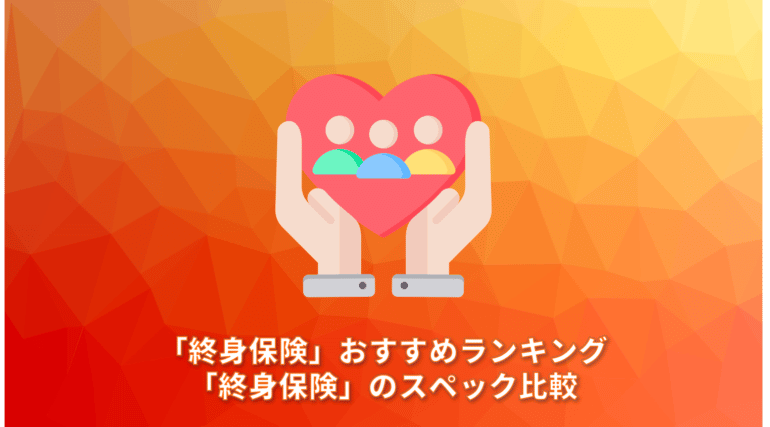



最新口コミ 口コミ投稿数:1件
本当は加入する予定はなかったのですが、保険の代理店の方に勧められて加入することにしました。月々の保険料は高めなのですが、解約した時に払い戻し金があることと貯蓄性があるということで掛け捨てではない安心感があり決めました。それと通院している状態だったので保険に入れるか心配していたのですが、オリックス生命なら入れる可能性があると保険の代理店の方に言われて申し込んだところ審査も無事に通ったので助かっています。