本ページはプロモーションが含まれています。
目次
- 「定期保険」おすすめ比較。ここがポイント!
- 「定期保険」の選び方
- 「定期保険」選び時のよくある質問
- 「定期保険」おすすめランキング/編集部
- 「定期保険」おすすめ比較
- 「定期保険」でおすすめのランキング/利用した方の口コミ・評判
- ライフネット生命/かぞくへの保険の評判・口コミ
- アクサダイレクト生命/定期保険2の評判・口コミ
- オリックス生命/ネット専用定期保険Bridge[ブリッジ](死亡保険)の評判・口コミ
- チューリッヒ生命/定期保険プレミアムDXの評判・口コミ
- メディケア生命/メディフィット定期の評判・口コミ
- はなさく生命/はなさく定期の評判・口コミ
- アクサ生命/ピュアライフの評判・口コミ
- メットライフ生命/スーパー割引定期保険の評判・口コミ
「定期保険」おすすめ比較。ここがポイント!
| サービス名 | ネット専用定期保険Bridge[ブリッジ](死亡保険) | 定期保険2 | かぞくへの保険 | メディフィット定期 | 定期保険プレミアムDX | 死亡保険FineSave[ファインセーブ] | スーパー割引定期保険 | ピュアライフ | はなさく定期 | 定期保険プラチナ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険料:40代男性・1,000万円 | 1,823円 | 1,910円 | 1,925円 | 1,847円 | 1,640円 | 2,670円 | 1,610円 | 4,160円 | 2,630円 | - |
「定期保険」の選び方
1.保険料が安い定期保険を選ぶ
定期保険は「掛け捨て型」の保険です。
貯蓄性はなく、万が一のことが起こらなければ、お金は戻ってこない特徴があります。その代わりに「保険料が安い」のが定期保険です。
定期保険は
- 死亡時
- 高度障害状態
のときに保険金が支払われるものですので、保障の違いはほとんどありません。
保障の内容が同じであれば、差が出てくるのは「保険料」ということになります。
- 同じ期間
- 同じ保険金額
という同じ条件の中で、一番安い保険料の定期保険が、一番おすすめということになります。
2.健康状態によって選ぶ定期保険を選ぶ
定期保険には
- 健康状態によって保険料が変わるタイプの定期保険
- 健康状態に関わらず保険料が決まるタイプの定期保険
があります。
健康状態によって保険料が変わるタイプの定期保険は
- 健康状態が良ければ、保険料が安い
- 健康状態が悪ければ、保険料が高い
というものになります。
つまり
- ご自身の健康状態が良い場合 → 健康状態によって保険料が変わるタイプの定期保険が保険料が安くなる可能性が高い
- ご自身の健康状態が悪い場合 → 健康状態に関わらず保険料が決まるタイプの定期保険が保険料が安くなる可能性が高い
ことになります。
ご自身の健康状態によって、選ぶべき定期保険は変わってくるのです。
3.特約によって定期保険を選ぶ
定期保険の場合は
- 保険金名称 支払事由の概要
- 死亡保険金 死亡したとき
- 高度障害保険金 病気またはケガにより約款所定の高度障害状態に該当したとき
というのが基本ですので、ここはどの定期保険でも大きな違いはありません。
差が出てくるのは「特約」です。
- リビング・ニーズ保険金:余命6か月以内と判断されたときに支払われる
- ストレス性疾病保障付就業不能保障特約(Z03):ストレス性疾病になった場合に支払われる
- 就業不能状態保険料払込免除特約:不慮の事故により約款所定の身体障害状態に該当された場合、以後の保険料の払込みは免除
- 生活障害保障型逓減定期保険特約:死亡したときや高度障害状態・要介護状態などに該当したときに保険金をお支払い
- 3大疾病保険料払込免除特約:3大疾病(がん・心疾患・脳血管疾患)で所定の事由に該当されたとき、以後の保険料の払込みを免除
- 災害割増特約:不慮の事故での死亡時に保険金を上乗せできる
様々な特約があります。
特約がある定期保険ほど、保険料が高くなっているため、保険料を重視するのであれば特約がない、少ない定期保険を選ぶ、保障を重視するのであれば特約が手厚い定期保険を選ぶのがおすすめです。
4.ネット保険か?対面型か?
生命保険には
- 通販型生命保険(ネット生保、オンライン、ダイレクト型)
- 対面型生命保険(コンサル型、店舗型)
の大きく分けて2つの種類があります。
通販型生命保険(ネット生保、オンライン、ダイレクト型)の特徴
- オンラインで申し込める
- 保険会社のコスト負担が少ない(人件費や店舗の家賃)分、保険料が安い
対面型生命保険(コンサル型、店舗型)の特徴
- 相談しながら加入する生命保険を決められる
「何に加入すべきか?」からわかっていない方、保険を相談しながら決めたい方は「対面型生命保険」がおすすめで、自分で加入したい生命保険の条件などが決まっている方は「通販型生命保険」がおすすめです。
「定期保険」選び時のよくある質問
Q.定期保険に解約返戻金ってありますか?
基本的に、定期保険に解約返戻金はありません。
定期保険は「掛け捨て」が基本ですので、途中解約しても、支払った保険料が戻ってこないのが一般的です。
一部、解約返戻金がある定期保険もありますが、戻ってくる金額はごくわずかですので、解約返戻金は期待できないものと理解して加入する必要があります。

その代わり、解約返戻金がある終身保険や養老保険と比較すると、圧倒的に保険料が安いのが定期保険なのです。
「定期保険」おすすめランキング/編集部

オリックス生命/ネット専用定期保険Bridgeブリッジ

-
- 保険料の安さ
- 5
-
- 安い保険料が設定されるハードルの低さ
- 5
-
- 特約の手厚さ
- 3
-
- サポートの手厚さ
- 3
-
- 付帯サービスの手厚さ
- 5
オリックス生命/ネット専用定期保険Bridgeブリッジがおすすめの理由
オリックス生命/ネット専用定期保険Bridgeブリッジがおすすめの理由は「保険料の安さ」「保険金額と保険期間を自由に設定可能」「医師の診査が不要」な点が挙げられます。
ネット専用定期保険Bridgeブリッジは、その名の通り「インターネット限定商品」として販売されているため、その分、保険料が安く設定されています。
また、医師の診査が不要で、最短即日で保障がスタートできる利便性と、保険金額と保険期間を自由に設定できる自由度を兼ね備えている点も大きなメリットと言えます。
デメリットは、特約は手薄な点です。
オリックス生命/ネット専用定期保険Bridgeブリッジの口コミ

アクサダイレクト生命/定期保険2

-
- 保険料の安さ
- 4
-
- 安い保険料が設定されるハードルの低さ
- 5
-
- 特約の手厚さ
- 4
-
- サポートの手厚さ
- 3
-
- 付帯サービスの手厚さ
- 4
アクサダイレクト生命/定期保険2がおすすめの理由
アクサダイレクト生命/定期保険2がおすすめの理由は「保険料の安さ」「保害割増特約がある」「健康診断書の提出が不要」な点が挙げられます。
定期保険2は、ネット型で保険料が安い点と不慮の事故での死亡時に保険金を上乗せできる特約「災害割増特約」が付帯されているメリットがあります。災害割増特約があることで、不慮の事故、火災、災害(台風、地震)、指定感染症(新型コロナウィルス等)での死亡・高度機能障害の場合も保険金が支払われます。
また、最大4,000万円まで健康診断書の提出が不要で加入できるなどのメリットもあります。
デメリットは、保険料は安いものの、業界1位、2位というわけではない点です。
アクサダイレクト生命/定期保険2の口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:3件
スマホで簡単に申し込みができ、約10分で完了しました。元々JAの保険に加入していましたが、保険料と保険内容の見直しを行い、金額が安く付帯内容も手厚いアクサダイレクト生命を選びました。特に、毎月の保険料は650円と破格の値段です。掛け捨てで運用もついていないですが、この価格であれば家計に安くとても助かっています。万が一の時の死亡保険金も納得のいく金額なので、安心して利用できています。保険金を生存中に受け取ることのできるオプションがあることも良い点です。
長年、アクサダイレクト生命にお世話になっています。若いころから入っているため、いまだに中身がよくわかっていないのが正直なところです。すべて担当者さん任せできてしまいましたが、近年その方が病に倒れ連絡つかず、他の方が対応してくれていますが、いまさら内容を詳しく聞くこともどうかとためらいながら、そのままつづけている状態です。ただ一つガッカリしてことがあります。私の両親もアクサさんなのですが長年続けてきたのに何の説明もなく、来年には年齢の問題で保険の補償がきれると言われ、急遽 他の保険会社さんに切り替えました。こちらのコンセプトには合わない回答だと思いますが開いてしまったので途中でやめるのも申し訳ないと思い回答しました。すみません。
10年間、15年間などライフプランに応じて保険期間を選択出来ることが魅力のひとつだと思います。子どもが小さいうちは、もしもの時に備えて保障を大きくしておき、子どもの自立後は保障を減額するつもりでいます。アクサダイレクトは、ネットでの申込がメインなので、他社の見積もりと比較したところ保険料が安かったです。リビングニーズ特約や、一定の保険金額まで診断書が不要などの特徴もあります。ただ、保険料が掛け捨てであるため、途中で解約してしまうとお金が戻ってこないことがデメリットとも感じます。

ライフネット生命/かぞくへの保険
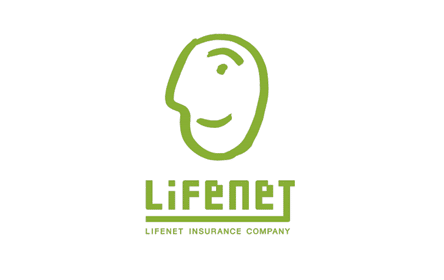
-
- 保険料の安さ
- 4
-
- 安い保険料が設定されるハードルの低さ
- 5
-
- 特約の手厚さ
- 3
-
- サポートの手厚さ
- 3
-
- 付帯サービスの手厚さ
- 3
ライフネット生命/かぞくへの保険がおすすめの理由
ライフネット生命/かぞくへの保険がおすすめの理由は「保険料の安さ」「保険金額・保険期間の自由度の高さ」です。
ライフネット生命は、インターネットで保険を提供するパイオニア的存在で、定期保険も、保険料の安さが大きなメリットとなっています。
また、保険金額(500万円~1億円)や保険期間(6種類)を自由に選択できるなど、自由度が高く、ウェブサイトで健康状態の質問事項に答えるだけで申込できる利便性の高い定期保険となっています。
デメリットは、特約や付帯サービスが手薄な点です。
ライフネット生命/かぞくへの保険の口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:4件
サイトもシンプルだし、補償もシンプルです。死亡保険金と年数を選ぶだけ。もっと色々つけたい気持ちもありましたが、保険料で普段の生活レベルが落ちるのも嫌だし、正直なところ何が必要かなんてわからないし、とりあえずもしもの時にまとまったお金が貰えればいいかなと思って加入しました。そういう意味では必要最低限で満足しています。ただ、WEBですむのが良いところではあるんですが、対面できる場所が近くにないので、その点は少し心配です。電話対応はきちんとしてくれる印象でしたが、新しい保険のようなので、実際どうなんだろうというのはあります。まあ、安い掛け捨てなのでそこまで心配する必要がないので良いかな、と思っています。
一定の期間、非常安価で加入しやすく、家族のために、本人が万が一のときの金額を用意する保険を用意できるのはありがたいです。ネットで簡単な告知で加入できるのでお手軽な保険としては有用です。ただ貯蓄や資産運用を考えている方には向いていないのでそこは注意してほしいと思います。使い方を割り切って一定期間安心を買うという保険なので貯蓄など資産運用には向いていません。ネット保険の中でもCMも放映しており、信頼度もある保険だと思います。
ライフネット生命の保険に決めた理由は学生時代の友人がその会社に勤めていたためです。周りの友人も学生時代の友人に保険の話を聞いて、保険に入っていたので、口コミ等も直接聞くことができ、また、わかりやすく保険のことについて詳しく教えてもらえたため、安心して加入することができました。月々の支払いも高すぎないのでこれからの将来のためにもしっかり保険に入っておくべきだなと感じております。早いうちに入る方がいいと思います!
まず第一に保険料の安さが魅力に感じています。月額の料金が、負担なく支払えるので、安心しています。オンラインで完結するから、人員が不要。そのために保険料が安くなっているのではないかと考えています。私の場合、タバコも吸わず、重い病気にもかかった経験がなかったことから、審査もスムーズに終わりました。オンラインで手軽かつ、リーズナブルな料金プラン、そして、審査も円滑であり、すべてにおいて大満足といえます。

メディケア生命/メディフィット定期

-
- 保険料の安さ
- 5
-
- 安い保険料が設定されるハードルの低さ
- 5
-
- 特約の手厚さ
- 3
-
- サポートの手厚さ
- 3
-
- 付帯サービスの手厚さ
- 5
メディケア生命/メディフィット定期がおすすめの理由
メディケア生命/メディフィット定期がおすすめの理由は「保険料の安さ」「付帯サービスの手厚さ」です。
メディフィット定期は、業界1位、2位を争う保険料の安さが大きなメリットとなっています。
また、オンライン診療サービス「curon(クロン)」を無料できる点もメリットと言えます。
デメリットは、保険料が安い代わりに、保険金額(300万円~3,000万円)や保険期間(10年、60歳まで、65歳まで、80歳まで)の選択肢が少なくなっています。
メディケア生命/メディフィット定期の口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:2件
メディケア生命は住友生命のグループ会社として誕生した保険会社です。
大手の保険会社ということで、信頼できる会社だと思いました。
定期保険は比較的保険料が安いと感じました。
保険内容がシンプルで分かりやすいという点が決め手となりました。
保険は色々とプランがあるとどれにしたらいいのか悩みがちですが、メディケア生命はそのような心配がないのがよかったです。
保険料が安いからいってサポートが充実していないわけではなく、他の保険会社と比べると保証内容もしっかりしているので安心できると感じました。
保険料は割と他社と比較すると安いのかなと思います。万一が無ければただの払い
損になってしまうのが生命保険だと捉えていますので、できるだけ安い方が良いと思いこの会社を選択しました。サポートはあまり手厚くないと思います。契約内容の確認書類が届くことはありますが、他は特にありませんでした。どういう内容かを丁寧に年1ぐらいは説明してくれる仕組みがあれば良いのになと思います。付帯サービスに関しても同様です。

チューリッヒ生命/定期保険プレミアムDX

-
- 保険料の安さ
- 5
-
- 安い保険料が設定されるハードルの低さ
- 3
-
- 特約の手厚さ
- 5
-
- サポートの手厚さ
- 5
-
- 付帯サービスの手厚さ
- 5
チューリッヒ生命/定期保険プレミアムDXがおすすめの理由
チューリッヒ生命/定期保険プレミアムDXがおすすめの理由は「保険料の安さ」「健康な方は保険料が割引」「特約が充実している」点です。
定期保険プレミアムDXは、保険料の安さが大きなメリットとなっています。さらに健康な方ほど保険料が割引になるタイプの定期保険で、健康な方ほどお得な設計となっています。
また、特約の数が多く、ストレス性疾病保障付就業不能保障特約(Z03)、就業不能状態保険料払込免除特約、リビング・ニーズ特約、指定代理請求特約などが利用できます。
デメリットは、加入年齢が満20歳~満49歳となっている点です。
チューリッヒ生命/定期保険プレミアムDXの口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:2件
チューリッヒ生命定期保険プレミアムに加入してますがかなりお得だと思います。
私は一番安いの規約しましたが月々1000円ぐらいで加入できて更新も10年更新や年齢別で契約できて自動更新もあるので便利だと思います。私の親も同じ保険でこの前保険金を受け取りましたが振り込みも早く対応もとても丁寧に対応していただきました。これから保険加入をご検討の方はチューリッヒ生命の定期保険プレミアムもいいと思うので参考にしてみてください。
毎月支払いする保険料が非常にリーズナブルなので全く負担にはならないですし、健康状態次第で更に安くしてもらえたのでとても助かっています。また、リーズナブルであっても保障が手厚いのでコストパフォーマンスは非常に高いですし、その他にもレンタカーや宿泊先の割引特典などサービス面も充実しているので、大変満足でした。そして、サポート体制もとても整っていて健康の悩みなどを相談する事ができましたし、何かあっても非常に安心感があります。

オリックス生命/死亡保険FineSave[ファインセーブ]

-
- 保険料の安さ
- 3
-
- 安い保険料が設定されるハードルの低さ
- 5
-
- 特約の手厚さ
- 3
-
- サポートの手厚さ
- 5
-
- 付帯サービスの手厚さ
- 4
オリックス生命/死亡保険FineSave[ファインセーブ]がおすすめの理由
オリックス生命/死亡保険FineSave[ファインセーブ]がおすすめの理由は「保険料の安さ」「保険金額と保険期間を自由に設定可能」な点が挙げられます。
オリックス生命/死亡保険FineSave[ファインセーブ]は、対面型の保険の中では、保険料が安く設定されています。
また、保険金額と保険期間を自由に設定できる自由度を兼ね備えている点も大きなメリットと言えます。
デメリットは、特約は手薄な点です。
オリックス生命/死亡保険FineSave[ファインセーブ]の口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:0件

メットライフ生命/スーパー割引定期保険

-
- 保険料の安さ
- 5
-
- 安い保険料が設定されるハードルの低さ
- 3
-
- 特約の手厚さ
- 3
-
- サポートの手厚さ
- 5
-
- 付帯サービスの手厚さ
- 5
メットライフ生命/スーパー割引定期保険がおすすめの理由
メットライフ生命/スーパー割引定期保険がおすすめの理由は「保険料の安さ」「健康な方は保険料が割引」「付帯サービスが充実している」点です。
スーパー割引定期保険は、保険料の安さが大きなメリットとなっています。さらに健康な方ほど保険料が割引になるタイプの定期保険で、最大約54%も健康な方は、保険料が割引になります。
また、メットライフ生命 クラブオフが利用できるため、国内のレジャー施設・宿泊がお得な価格で利用可能です。
デメリットは、健康じゃない方は保険料が割高になってしまう点です。
メットライフ生命/スーパー割引定期保険の口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:1件
週刊誌の保険特集で一番評価が高かったので加入しました。保険は掛け捨てが一番効率が良いと考えていて、さらにタバコを吸わなかったりすればより安い保険料で加入できるこの保険を選びました。いまは特に低金利で、保険の金利も低いので積み立てタイプの保険に加入しても旨味がないと思うので、保障が必要な期間、必要な額を手頃な保険料で用意できる定期保険が良いと思いました。保険料が浮いた分は、積み立てNISAなどを活用した投資に回すことで、効率的に貯めることができると考えています。

アクサ生命/ピュアライフ

-
- 保険料の安さ
- 2
-
- 安い保険料が設定されるハードルの低さ
- 4
-
- 特約の手厚さ
- 5
-
- サポートの手厚さ
- 5
-
- 付帯サービスの手厚さ
- 5
アクサ生命/ピュアライフがおすすめの理由
アクサ生命/ピュアライフがおすすめの理由は「保険料の安さ」「終身保険に加入し直せる」「年金払特約で年金を受け取れる」点です。
ピュアライフは、所定の条件を満たせば、被保険者の健康状態にかかわらず、保障が一生涯続く無配当終身保険に加入し直すことができる、「年金払特約」を中途付加することにより、保険金の全部または一部を複数年にわたって年金で受けるとことができるなど、通常の定期保険を途中で終身保険にしたり、個人年金の特約をつけたりできる定期保険です。自由度の高い定期保険と言えます。
デメリットは、保険料が高い点です。「年金払特約」などを付けると保険料が上がります。
アクサ生命/ピュアライフの口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:1件
アクサ生命のピュアライフはとにかくシンプルな保障内容で保険料がお手頃なのが最大の魅力でした。また、保障してもらう期間を自由に選べたり、終身保険への切り替えも簡単かつ自由にできるところもフレキシブルだと思います。解約返戻金はありませんがその分、保険料が安く、更新による保険料の値上がりもないので安心して細く長く続けやすいです。中途の付加契約によって保険金を年金で受け取るシステムもつけられるので、長い老後の資金のやりくりの選択肢として残せる自由度が高いのも良い保険だと思っています。

はなさく生命/はなさく定期

-
- 保険料の安さ
- 2
-
- 安い保険料が設定されるハードルの低さ
- 3
-
- 特約の手厚さ
- 4
-
- サポートの手厚さ
- 4
-
- 付帯サービスの手厚さ
- 4
はなさく生命/はなさく定期がおすすめの理由
はなさく生命/はなさく定期がおすすめの理由は「保険料の安さ」「保険料の払込みを免除する特約がある」点です。
はなさく定期は、対面型の生命保険の中では、保険料が安く設定されています。また、上皮内がんを含む3大疾病(がん、心疾患、脳血管疾患)で所定の事由に該当されたとき、以後の保険料が発生しない「3大疾病保険料払込免除特約」を付けることができます。
保障と保険料のバランスが取れた定期保険と言えます。
デメリットは、ネット型の定期保険と比較すると、保険料が高い点です。
はなさく生命/はなさく定期の口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:1件
「はなさく生命」という聞き慣れない保険会社で、最初は加入にとても不安がありました。しかし、スタッフの説明やネットの情報などから保険業界最大手の日本生命グループの1つだと知り、信頼できる保険会社だと確信しました。やはり、将来の保障を考える上で、心配な点は一つでも無くしておきたい。大手の保険会社なら、保障も充実しているだろうし、自分の身に万が一のことがあった場合、色々とサポートしてくれそうなので安心です。

チューリッヒ生命/定期保険プラチナ

-
- 保険料の安さ
- 3
-
- 安い保険料が設定されるハードルの低さ
- 3
-
- 特約の手厚さ
- 5
-
- サポートの手厚さ
- 5
-
- 付帯サービスの手厚さ
- 5
チューリッヒ生命/定期保険プラチナがおすすめの理由
チューリッヒ生命/定期保険プラチナがおすすめの理由は「保険料の安さ」「満50~80歳が対象」「特約が充実している」点です。
定期保険プラチナは、満50~80歳が対象の定期保険です。年齢が高齢になるほど加入できない生命保険もありますが、高齢になっても加入できる定期保険という特徴があります。
また、特約の数が多く、特定疾病保険料払込免除特約【3大疾病型】【5大疾病型】、災害割増特約(Z02)、リビング・ニーズ特約などが利用できます。
デメリットは、保険料は高い点です。
チューリッヒ生命/定期保険プラチナの口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:0件
「定期保険」おすすめ比較
| サービス名 | ネット専用定期保険Bridge[ブリッジ](死亡保険) | 定期保険2 | かぞくへの保険 | メディフィット定期 | 定期保険プレミアムDX | 死亡保険FineSave[ファインセーブ] | スーパー割引定期保険 | ピュアライフ | はなさく定期 | 定期保険プラチナ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運営会社 | オリックス生命 | アクサダイレクト生命 | ライフネット生命 | メディケア生命 | チューリッヒ生命 | オリックス生命 | メットライフ生命 | アクサ生命 | はなさく生命 | チューリッヒ生命 |
| 保険料:30代男性・1,000万円 | 974円 | 1,050円 | 1,068円 | 977円 | 970円 | 1,690円 | 840円 | 2,780円 | 1,770円 | - |
| 保険料:40代男性・1,000万円 | 1,823円 | 1,910円 | 1,925円 | 1,847円 | 1,640円 | 2,670円 | 1,610円 | 4,160円 | 2,630円 | - |
| 保険料:50代男性・1,000万円 | 2,611円 | 4,160円 | 4,217円 | 4,012円 | - | 5,020円 | 3,350円 | 6,270円 | 4,880円 | 4,340円 |
| 保険料試算条件補足 | - | - | - | - | 非喫煙、標準体型 | - | 過去2年非喫煙、標準体型 | 65歳満了 | 3大疾病保険料払込免除特約付与なし、3大疾病保険料払込免除特約 | - |
| 保険料特徴 | - | - | - | - | 健康な方は保険料が割引 20歳~49歳まで | - | 健康状態によって4段階で、最大約54%保険料が安くなる | 終身保険への変更、年金の特約を追加できる | - | 50歳から80歳まで |
| 特約 | リビング・ニーズ保険金 | リビング・ニーズ保険金 災害割増特約 | リビング・ニーズ保険金 | リビング・ニーズ保険金 | ストレス性疾病保障付就業不能保障特約(Z03) 就業不能状態保険料払込免除特約 リビング・ニーズ特約 指定代理請求特約 | リビング・ニーズ保険金 | リビング・ニーズ保険金 | リビング・ニーズ保険金 生活障害保障型逓減定期保険特約 指定代理請求特約 | リビング・ニーズ保険金 3大疾病保険料払込免除特約 | 特定疾病保険料払込免除特約【3大疾病型】【5大疾病型】 災害割増特約(Z02) リビング・ニーズ特約 |
| 解約払戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他サービス | セカンドオピニオン 糖尿病専門サポート 介護・認知症サポート 重症化・再発予防カウンセリング | メディカルコールサポート24 メディカルコンサルテーション | - | 無料のオンライン診療サービス 24時間電話健康相談サービス 女性のための24時間電話健康相談サービス セカンドオピニオンサービス 受診手配・紹介サービス | チューリッヒ生命Club Off Doctors Me メディカルサポート 障害年金サポート | セカンドオピニオン 糖尿病専門サポート 介護・認知症サポート 重症化・再発予防カウンセリング | 健康生活サポートダイアル 早期発見サポートダイアル 治療時のサポートダイアル 治療中・治療後のケアダイアル くらしの相談ダイアル メットライフ生命 クラブオフ | オンライン健康相談 24時間電話健康相談 セカンドオピニオンサービス 介護・リハビリサポートサービス 糖尿病サポートサービス 郵送検査キットによる血液検査サービス ホスピタルサーチ | ご遺族安心サポート | チューリッヒ生命Club Off Doctors Me メディカルサポート 障害年金サポート |
| 公式 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
| 口コミ | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 |
「定期保険」でおすすめのランキング/利用した方の口コミ・評判
口コミ・評判ランキングは、口コミ件数5件以上で、総合評価順に表示しています。口コミ件数5件未満のものは、口コミ件数が多い順に表示しています。
ライフネット生命/かぞくへの保険の評判・口コミ
口コミ総合評価
6.2点
総合評価(10点満点)
最新口コミ 口コミ投稿数:4件
サイトもシンプルだし、補償もシンプルです。死亡保険金と年数を選ぶだけ。もっと色々つけたい気持ちもありましたが、保険料で普段の生活レベルが落ちるのも嫌だし、正直なところ何が必要かなんてわからないし、とりあえずもしもの時にまとまったお金が貰えればいいかなと思って加入しました。そういう意味では必要最低限で満足しています。ただ、WEBですむのが良いところではあるんですが、対面できる場所が近くにないので、その点は少し心配です。電話対応はきちんとしてくれる印象でしたが、新しい保険のようなので、実際どうなんだろうというのはあります。まあ、安い掛け捨てなのでそこまで心配する必要がないので良いかな、と思っています。
一定の期間、非常安価で加入しやすく、家族のために、本人が万が一のときの金額を用意する保険を用意できるのはありがたいです。ネットで簡単な告知で加入できるのでお手軽な保険としては有用です。ただ貯蓄や資産運用を考えている方には向いていないのでそこは注意してほしいと思います。使い方を割り切って一定期間安心を買うという保険なので貯蓄など資産運用には向いていません。ネット保険の中でもCMも放映しており、信頼度もある保険だと思います。
ライフネット生命の保険に決めた理由は学生時代の友人がその会社に勤めていたためです。周りの友人も学生時代の友人に保険の話を聞いて、保険に入っていたので、口コミ等も直接聞くことができ、また、わかりやすく保険のことについて詳しく教えてもらえたため、安心して加入することができました。月々の支払いも高すぎないのでこれからの将来のためにもしっかり保険に入っておくべきだなと感じております。早いうちに入る方がいいと思います!
まず第一に保険料の安さが魅力に感じています。月額の料金が、負担なく支払えるので、安心しています。オンラインで完結するから、人員が不要。そのために保険料が安くなっているのではないかと考えています。私の場合、タバコも吸わず、重い病気にもかかった経験がなかったことから、審査もスムーズに終わりました。オンラインで手軽かつ、リーズナブルな料金プラン、そして、審査も円滑であり、すべてにおいて大満足といえます。
アクサダイレクト生命/定期保険2の評判・口コミ
口コミ総合評価
5.8点
総合評価(10点満点)
最新口コミ 口コミ投稿数:3件
スマホで簡単に申し込みができ、約10分で完了しました。元々JAの保険に加入していましたが、保険料と保険内容の見直しを行い、金額が安く付帯内容も手厚いアクサダイレクト生命を選びました。特に、毎月の保険料は650円と破格の値段です。掛け捨てで運用もついていないですが、この価格であれば家計に安くとても助かっています。万が一の時の死亡保険金も納得のいく金額なので、安心して利用できています。保険金を生存中に受け取ることのできるオプションがあることも良い点です。
長年、アクサダイレクト生命にお世話になっています。若いころから入っているため、いまだに中身がよくわかっていないのが正直なところです。すべて担当者さん任せできてしまいましたが、近年その方が病に倒れ連絡つかず、他の方が対応してくれていますが、いまさら内容を詳しく聞くこともどうかとためらいながら、そのままつづけている状態です。ただ一つガッカリしてことがあります。私の両親もアクサさんなのですが長年続けてきたのに何の説明もなく、来年には年齢の問題で保険の補償がきれると言われ、急遽 他の保険会社さんに切り替えました。こちらのコンセプトには合わない回答だと思いますが開いてしまったので途中でやめるのも申し訳ないと思い回答しました。すみません。
10年間、15年間などライフプランに応じて保険期間を選択出来ることが魅力のひとつだと思います。子どもが小さいうちは、もしもの時に備えて保障を大きくしておき、子どもの自立後は保障を減額するつもりでいます。アクサダイレクトは、ネットでの申込がメインなので、他社の見積もりと比較したところ保険料が安かったです。リビングニーズ特約や、一定の保険金額まで診断書が不要などの特徴もあります。ただ、保険料が掛け捨てであるため、途中で解約してしまうとお金が戻ってこないことがデメリットとも感じます。
オリックス生命/ネット専用定期保険Bridge[ブリッジ](死亡保険)の評判・口コミ
口コミ総合評価
6.6点
総合評価(10点満点)
最新口コミ 口コミ投稿数:2件
ネットで申し込みができるので、思い立ってすぐには入れて簡単でした。保険料も安かったです。保険期間を自分で決めることができるし、月々の支払いが抑えらるので、子供にお金がかかる家庭も安心して入れます。自分の判断で入るので不安はありました。問い合わせの電話はつながりにくいし、回されるので、納得のいく回答はもらえなかったのは残念でした。安いからいいかなという軽い気持ちで入ったので、保障内容をきちんと理解していない部分もあります。
オリックス生命/ネット専用定期保険Bridge[ブリッジ](死亡保険)は、インターネットで手軽に申し込めますし、告知画面で健康状態について答えるだけで、医師の診査が不要なので楽だと思いました。また、保険料も掛け捨てという事で少額な方ですし、掛け捨てとしてもリーズナブルですのでお得感があります。同じ企業の「ファインセーブ」と迷いましたが、保険期間がやや短かったので健康に自信がない自分には最適かと思い決めました。
チューリッヒ生命/定期保険プレミアムDXの評判・口コミ
口コミ総合評価
6.1点
総合評価(10点満点)
最新口コミ 口コミ投稿数:2件
チューリッヒ生命定期保険プレミアムに加入してますがかなりお得だと思います。
私は一番安いの規約しましたが月々1000円ぐらいで加入できて更新も10年更新や年齢別で契約できて自動更新もあるので便利だと思います。私の親も同じ保険でこの前保険金を受け取りましたが振り込みも早く対応もとても丁寧に対応していただきました。これから保険加入をご検討の方はチューリッヒ生命の定期保険プレミアムもいいと思うので参考にしてみてください。
毎月支払いする保険料が非常にリーズナブルなので全く負担にはならないですし、健康状態次第で更に安くしてもらえたのでとても助かっています。また、リーズナブルであっても保障が手厚いのでコストパフォーマンスは非常に高いですし、その他にもレンタカーや宿泊先の割引特典などサービス面も充実しているので、大変満足でした。そして、サポート体制もとても整っていて健康の悩みなどを相談する事ができましたし、何かあっても非常に安心感があります。
メディケア生命/メディフィット定期の評判・口コミ
口コミ総合評価
5.9点
総合評価(10点満点)
最新口コミ 口コミ投稿数:2件
メディケア生命は住友生命のグループ会社として誕生した保険会社です。
大手の保険会社ということで、信頼できる会社だと思いました。
定期保険は比較的保険料が安いと感じました。
保険内容がシンプルで分かりやすいという点が決め手となりました。
保険は色々とプランがあるとどれにしたらいいのか悩みがちですが、メディケア生命はそのような心配がないのがよかったです。
保険料が安いからいってサポートが充実していないわけではなく、他の保険会社と比べると保証内容もしっかりしているので安心できると感じました。
保険料は割と他社と比較すると安いのかなと思います。万一が無ければただの払い
損になってしまうのが生命保険だと捉えていますので、できるだけ安い方が良いと思いこの会社を選択しました。サポートはあまり手厚くないと思います。契約内容の確認書類が届くことはありますが、他は特にありませんでした。どういう内容かを丁寧に年1ぐらいは説明してくれる仕組みがあれば良いのになと思います。付帯サービスに関しても同様です。
はなさく生命/はなさく定期の評判・口コミ
口コミ総合評価
10.0点
総合評価(10点満点)
最新口コミ 口コミ投稿数:1件
「はなさく生命」という聞き慣れない保険会社で、最初は加入にとても不安がありました。しかし、スタッフの説明やネットの情報などから保険業界最大手の日本生命グループの1つだと知り、信頼できる保険会社だと確信しました。やはり、将来の保障を考える上で、心配な点は一つでも無くしておきたい。大手の保険会社なら、保障も充実しているだろうし、自分の身に万が一のことがあった場合、色々とサポートしてくれそうなので安心です。
アクサ生命/ピュアライフの評判・口コミ
口コミ総合評価
7.4点
総合評価(10点満点)
最新口コミ 口コミ投稿数:1件
アクサ生命のピュアライフはとにかくシンプルな保障内容で保険料がお手頃なのが最大の魅力でした。また、保障してもらう期間を自由に選べたり、終身保険への切り替えも簡単かつ自由にできるところもフレキシブルだと思います。解約返戻金はありませんがその分、保険料が安く、更新による保険料の値上がりもないので安心して細く長く続けやすいです。中途の付加契約によって保険金を年金で受け取るシステムもつけられるので、長い老後の資金のやりくりの選択肢として残せる自由度が高いのも良い保険だと思っています。
メットライフ生命/スーパー割引定期保険の評判・口コミ
口コミ総合評価
6.6点
総合評価(10点満点)
最新口コミ 口コミ投稿数:1件
週刊誌の保険特集で一番評価が高かったので加入しました。保険は掛け捨てが一番効率が良いと考えていて、さらにタバコを吸わなかったりすればより安い保険料で加入できるこの保険を選びました。いまは特に低金利で、保険の金利も低いので積み立てタイプの保険に加入しても旨味がないと思うので、保障が必要な期間、必要な額を手頃な保険料で用意できる定期保険が良いと思いました。保険料が浮いた分は、積み立てNISAなどを活用した投資に回すことで、効率的に貯めることができると考えています。
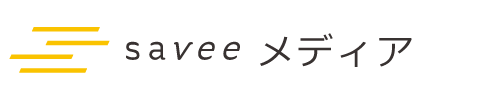




最新口コミ 口コミ投稿数:2件
ネットで申し込みができるので、思い立ってすぐには入れて簡単でした。保険料も安かったです。保険期間を自分で決めることができるし、月々の支払いが抑えらるので、子供にお金がかかる家庭も安心して入れます。自分の判断で入るので不安はありました。問い合わせの電話はつながりにくいし、回されるので、納得のいく回答はもらえなかったのは残念でした。安いからいいかなという軽い気持ちで入ったので、保障内容をきちんと理解していない部分もあります。
オリックス生命/ネット専用定期保険Bridge[ブリッジ](死亡保険)は、インターネットで手軽に申し込めますし、告知画面で健康状態について答えるだけで、医師の診査が不要なので楽だと思いました。また、保険料も掛け捨てという事で少額な方ですし、掛け捨てとしてもリーズナブルですのでお得感があります。同じ企業の「ファインセーブ」と迷いましたが、保険期間がやや短かったので健康に自信がない自分には最適かと思い決めました。