本ページはプロモーションが含まれています。
目次
「学資保険」おすすめ比較。ここがポイント!
| サービス名 | ニッセイ学資保険 | つみたて学資 | みらいのつばさ | 学資保険 | 5年ごと利差配当付こども保険 | &LIFE こども保険 | こども応援団・Mickey | スミセイのこどもすくすく保険 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 返戻率 | 104.0% | 104.7% | 104.7% | 104.9% | - | - | 102.7% | 101.7% |
「学資保険」の選び方
1.返戻率の多さ
学資保険は
保険料を支払っていれば、大学入学時などの決まったタイミングで満期保険金・年金・祝金が受け取れる保険のこと
を言います。
貯蓄性のある保険です。
重要になるのは「貯蓄性の高さ」 = 「返戻率の高さ」
です。
払った保険料に対して、受取総額がどのくらい戻ってくるかの割合「返戻率」が高い学資保険がおすすめの保険と言えます。
2.保険料の安さ
学資保険の場合は、保険料が安ければ良いというわけではなく、返戻率の高い方が良い保険、お得な保険と言えます。
しかしながら、いくら返戻率が高くても、保険料が高く、払えないのでは意味がありません。
一般的に
保険料の払込期間が短い = 保険料が高い = 返戻率が高い
という関係になっています。
無理をしない範囲で払える保険料の学資保険を選ぶ必要があります。
3.選択肢の多さ
学資保険の設計では
お金の受け取るタイミングや方法は、以下のものがあります。
- 幼稚園の入園のタイミングで「祝い金」として
- 小学校の入学のタイミングで「祝い金」として
- 中学校の入学のタイミングで「祝い金」として
- 高校入学のタイミングで「祝い金」として
- 大学の入学のタイミングで「祝い金」として
- 成人の入学のタイミングで「祝い金」として
- 大学入学中に「年金」として
- 大学卒業のタイミングで「満期保険金」として
また、保険料の支払い方は
- 月払い
- 年払い
保険料払込期間は
- ○歳まで
割引・特約
- 医療特約
- 兄弟割引
- 指定代理請求特約
と、様々な選択肢があり、選択の仕方によって、保険料と返戻率が大きく変わってきます。
選べる選択肢が多い学資保険の方が、ご自身の望む保険料、保険金の受け取り方が可能になります。
「学資保険」選び時のよくある質問
Q.教育資金を貯める保険として「学資保険」は適切ですか?
日本では、低金利を誘導する金融緩和が20年、30年続いています。
銀行の預金金利が低いのも、これが要因です。
銀行の預金金利が低ければ、学資保険の返戻率もかなり下がっているのが現状なのです。
しかし、学資保険のいいところは
- 半ば強制的に保険料を払い続ければ、教育資金・学費が必要なタイミングで受け取れる
という「強制性」です。
普通に貯金した方が良いという方もいますが、きちんと定期的に貯金できるのか?はわかりません。途中で魔が差して別のモノに使ってしまうかもしれないのです。
また、投資の方が高い利回りで運用できますが、元本が毀損する(減ってしまう)リスクも内在します。学資保険であれば、返戻率が100%を超えていれば、元本が減ることはないのです。

金利は低いものの、学資保険で教育資金を準備するというのは、賢い選択肢の一つではあるのです。
「学資保険」おすすめランキング/編集部

日本生命/ニッセイ学資保険

-
- 保険料の安さ
- 3
-
- 返戻率の多さ
- 5
-
- 選択肢の多さ
- 5
-
- 特約・オプションの多さ
- 4
-
- サポートの手厚さ
- 5
日本生命/ニッセイ学資保険がおすすめの理由
日本生命/ニッセイ学資保険がおすすめの理由は「契約件数40万件超の実績」「返戻率の高さ」です。
日本生命/ニッセイ学資保険は、業界1位、2位を争う返戻率の高さを実現しており、結果として、契約件数40万件超の実績を誇ります。多くの方に選べている学資保険とも言えます。
また、小学校入学、中学校入学、高校入学時の祝金の有無を選べるので、細かく条件設定が可能なメリットもあります。
デメリットは、払込期間を5年を選択すると返戻率がかなり高くなる反面、保険料も高額になる点です。
日本生命/ニッセイ学資保険の口コミ

明治安田生命/つみたて学資

-
- 保険料の安さ
- 5
-
- 返戻率の多さ
- 5
-
- 選択肢の多さ
- 4
-
- 特約・オプションの多さ
- 3
-
- サポートの手厚さ
- 4
明治安田生命/つみたて学資がおすすめの理由
明治安田生命/つみたて学資がおすすめの理由は「契約件数200万件超の実績」「返戻率の高さ」です。
明治安田生命/つみたて学資は、業界1位、2位を争う返戻率の高さを実現しており、結果として、契約件数200万件超の実績を誇ります。多くの方に選べている学資保険とも言えます。
また、契約時の一括払いという選択肢もあり、その場合、返戻率がかなり高くなります。
デメリットは、払込期間が最長15歳までですので、返戻率がかなり高くなる反面、保険料も高額になる点大学までの期間の祝金がない点です。
明治安田生命/つみたて学資の口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:8件
私は、明治安田生命の「つみたて学資」を利用した学資保険に加入しています。この学資保険には、毎月少額の保険料を支払い、将来的な教育費を貯めることができる仕組みがあります。
利用していて良かった点は、まず、保険料が毎月の支払い額が少額であることです。これにより、教育費の負担が大きくなりすぎず、家計を圧迫することがなくなりました。
また、学資保険の選択肢が多く、自分に合ったプランを選べる点も魅力的でした。さらに、学資保険の契約期間が長く、将来的な教育費の負担を少なくすることができる点も大きなメリットです。
一方、悪かった点としては、保険金が払い戻されるまでに契約期間が必要なことがあります。また、保険料を長期間払い続ける必要があるため、収入が不安定な場合は支払いが困難になることがあります。
総じて、明治安田生命の「つみたて学資」は、将来の教育費を負担せずに貯めることができる学資保険であり、毎月少額の支払いで教育費の負担を軽減することができます。ただし、長期的な視点で契約することが必要であり、自分に合ったプランを選択することが重要です。
チューリッヒ生命のがん保険加入前に利用していたがん保険と比べてみると保証ないようがほとんど変わらないのに保険料が2割程安く年間の掛け金に結構さ差額があったので変えて良かったです。また、加入時は、電話で案内をお願いするとすぐに対応してくれ資料などすぐに送ってくださいました。また、電話対応もすごくよく的確に説明してくれ、説明内容も分かりやすかったです。保険内容も、もしがんになった時でもこの保険である程度は対応でき家族思いの保険だなと感じました。
上の世代の身内が皆ガンになっているので、ガン保険は必須だと思っています。何年も払っていて、まだ一度も申請したことはないですが、安心を得るため、かなり手厚いものにしています。いくつも比較して、値段の割に手厚いものを選んだのがチューリッヒの保険です。最近は、入院が必要でないことも多いみたいなので、通院治療の費用のでるものを選びました。実際、最近、身内がガンの治療のため毎日通院が必要になったので、やはり通院ででる保険にしていてよかったなと感じています。
保険金額の選択肢が広く、いろいろな状況をあわせて設定できるのが助かる。また、保険医金の支払いがはやく、就業不能状態でお金をかせげなくなった時に非常に助けていただいた。またネットで手続きを完了させられるところも、まともに動けない状態になっていた時は非常に助かる。このような上質なサービスが、他者と比較して安く受けられる点が、中流層には嬉しい。担当者によりけりかもしれないが、私の時は物腰のよい人で、不快な思いをすることなく話を勧められた。
子供が生まれると同時に学資保険に入りました。子供が生まれたら、すぐ入るのが親の務めだよと両親に口酸っぱく言われたことを思い出します。子供本人が中学三年生になるまでに、300万円程度貯めるタイプの学資保険に入りました。友人の母親が、明治安田生命に勤めていたので、その縁で入りました。月々の払い込みが自動的に行われるので、そのお金は元々ないものとして毎日の生活を計画的に過ごしていました。子供の進学時のお金に困るということだけは避けることができました。子供が生まれたら、すぐに学資保険加入!!大切な合言葉です。

フコク生命/みらいのつばさ

-
- 保険料の安さ
- 5
-
- 返戻率の多さ
- 3
-
- 選択肢の多さ
- 5
-
- 特約・オプションの多さ
- 4
-
- サポートの手厚さ
- 4
フコク生命/みらいのつばさがおすすめの理由
フコク生命/みらいのつばさがおすすめの理由は「返戻率の高さ」「祝金の受け取り方が選べる」点です。
フコク生命/みらいのつばさは、業界トップクラスの返戻率の高さを実現しています。また、細かく祝い金が受け取れるS(ステップ)型と、大学入学と満期保険金だけ受け取れるJ(ジャンプ)型が用意されています。
また、兄弟割引があるため、兄弟姉妹が加入する場合には、保険料が割引になる特典もあります。
デメリットは、とくにありません。
フコク生命/みらいのつばさの口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:6件
ハーフタイプを選択して加入しているので、毎月の保険料はとにかくリーズナブルで全く負担に感じる事がないですし、それでいて精神的な疾患まで保障されるので、この対象の幅広さはとても安心感があります。また、リーズナブルなので仕方ないとは言え、掛け捨てなのはやはり気にはなりましたが、今後保険料が変わる事もずっとないですし、健康について医師の方に直接相談ができるサービスもあり、万が一働けなくなった時の備えとしては十分に満足できています。
子どもを妊娠、出産を機に学資保険等について調べ始めました。日頃お世話になっている保険屋さんに相談し、候補として挙がったのがフコク生命のみらいのつばさです。自分がネットで調べた際にも口コミ等で評価を知っておりましたので安心でした。主人が特定の生命保険に加入していないことと、返戻率でこちらを選択し、払い戻しの期間はまだまだ先ですが現状不満はありません。選択肢やオプション等が充実しているとは感じませんが、保険料については満足しています。大きな企業ですので、サポートに関しては充実しています。
積み立てていく保険ですが、払込期間が10年になっており、早めに払い込みを終えるので返礼率が少し高くなります。兄弟がいるので、早めに払い込みを終えたいと思い選びました。わが家では祝い金を受け取れるタイプにしています。大学受験で一番お金が必要になりますが、中学入学や高校入学時にはまとまったお金が必要になります。子供の学用品を揃えるのに使えるので助かります。他に準備はしていないのでとても頼りにしています。
対応して説明してくださる方がとても丁寧だったので、学資保険に入りました。夫が急死したり事故に合ったりしたときなどの、いざという時には役に立つかもしれないとおもいました。何事もなければ貯金にもなります。子どもが18歳になり満期を迎え、300万円の支払いがありました。子どもが丁度大学受験の時だったので、受験料、交通費、宿泊費、入学金、授業料、マンションの入居費、新生活ための色々な物品購入のために、本当に役に立ちました。学資保険に入っていて良かったと思いました。毎月の支払金額は多くはありませんが、18年間積み立てることで大きな金額になっていてびっくりしました。
私は子どもが生まれて半年ほどでフコク生命の学資保険に加入しました。誰かに勧められたわけではなくて自分でどの学資保険がいいか調べたうえでフコク生命にしました。その当時たくさんある学資保険の中で年払いにすると返戻率が良かったことや契約者(親)にもしものことがあった時に保障は継続するけど保険料の払い込みは免除になる特約がついていたのが一番の決め手になりました。また大きい会社なので安心感や信頼感もあり加入して本当に良かったと思います。

ソニー生命/学資保険

-
- 保険料の安さ
- 3
-
- 返戻率の多さ
- 4
-
- 選択肢の多さ
- 4
-
- 特約・オプションの多さ
- 4
-
- サポートの手厚さ
- 3
ソニー生命/学資保険がおすすめの理由
ソニー生命/学資保険がおすすめの理由は「返戻率の高さ」「祝金の受け取り方が選べる」点です。
ソニー生命/学資保険は、業界トップクラスの返戻率の高さを実現しています。また、保険料払込期間を長くしても、一定の返戻率を維持しているお得な学資保険と言えます。
また、大学の在学中に受け取る、大学の入学資金として受け取る、中学・高校・大学の入学資金として受け取るなど、多くの受け取り方を選択できるメリットがあります。
デメリットは、とくにありません。
ソニー生命/学資保険の口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:16件
子どもが産まれて半年後に契約しました。産婦人科に置かれている雑誌で何となく目にしていて、それまでは学資保険なんて無縁で全く興味も知識もありませんでしたが、調べてみると学資保険の中でもかなり返戻率が高いことが分かり、評判もとても良く、契約内容もシンプルで分かりやすかったので、一番返戻率が高くなるように前期前納払いで契約しました。担当の方もとても感じがよく親身で、他の保険を勧められるようなこともなかったです。
お世話になっている保険会社の人のお付き合いで勧められ、加入いたしました。他にも色々な学資保険はあったとは思うのですが、自分が聞いたことがある保険会社ですし、知人にも加入している人が多かったので加入したのですが、当時は無知でよくわからなかったのですが、色々みてわかったことは、ごくごく平均点だと思います。特約も他と変わらず、特色も特に和えうわけではないので、とりあえず何かに加入したいという方にはいいと思います。
貯金がなかなか出来なくて、引き落としでコツコツと積み立てていける学資保険を選びました。家計が苦しくて保険金を支払えない月があっても、翌月に払っても大丈夫な制度もあってとても助かりました。気がついたら子どもも18才になり、進学の費用にあてることができて、ほっとしています。親が病気やけがで働けない場合も、救済措置があるのは本当に助かると思います。今の世の中、明日何があるかわからないですから、最低限の保険は掛けていたほうが良いと思います。
ソニー生命の保険に加入しております。元々インターネットの保険ということで、ネット上でほとんどのことが完結するものと思い込んでいたのですが、実際には営業の方に何度も自宅まで足を運んで頂き、丁寧にご説明をして頂きました。おかげで、不明点や疑問点、不安な点などを解消して、保険に加入することができたと思っています。また加入後も、よくありがちな、入ったら入りっぱなしということはなく、丁寧にアフターフォローもして頂いて、加入保険の状況などのご説明も頂いています。以上のことから、私は非常に満足をしています。
保障内容が充実しているため、安心して加入できます。また、保険金の運用実績が良いため、将来の教育費用を確実に賄えるという点も高く評価できます。
一方で、保険料が高いと思います。また、保険金の支払いが始まる時期が限定されているため、子供が大学に進学する前に亡くなった場合は保険金を受け取れないというデメリットもあります。
総合的に考えると、ソニー生命/学資保険は将来の教育費用に備えるための有力な商品であり、保障内容や運用実績の良さからおすすめです。ただし、保険料や支払い時期に関する制限については事前によく確認しておくことが重要です。

東京海上日動あんしん生命/5年ごと利差配当付こども保険
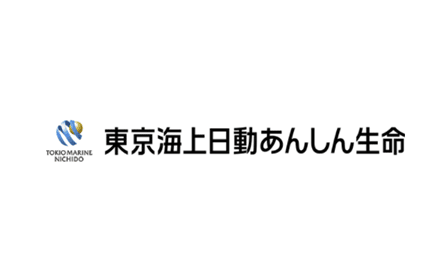
-
- 保険料の安さ
- 5
-
- 返戻率の多さ
- 2
-
- 選択肢の多さ
- 3
-
- 特約・オプションの多さ
- 3
-
- サポートの手厚さ
- 4
東京海上日動あんしん生命/5年ごと利差配当付こども保険がおすすめの理由
東京海上日動あんしん生命/5年ごと利差配当付こども保険がおすすめの理由は「死亡給付金、災害死亡保険金、養育年金がでる」点です。
東京海上日動あんしん生命/5年ごと利差配当付こども保険は、災害死亡保険金、死亡給付金、養育年金が出る死亡保険の特徴を持った学資保険です。また、5年ごとに積立配当金が出ます。積立配当金は、運用実績によって増減し、配当ゼロということもあるものです。
デメリットは、積立配当金がいくら出るかはわからない点です。
東京海上日動あんしん生命/5年ごと利差配当付こども保険の口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:2件
現在休職理由として増加しているうつ病などの精神疾患に関しては補償されないためあまり現代社会に適していない補償内容だと思います。また、給付金がでるための条件が障害等級1~2級に該当しないといけないという点もよくないと思います。さらに、今はよく聞く保険料払込免除特約もないので三大疾病にかかった時に保険料の支払いが続くという経済的な不安も拭えません。逆に、重度の病気やケガにかかった場合には頼りになる補償だと思います。
私が勤めている会社は不安定な業界でリストラや給料カットが定期的に行われている会社です。そのため家庭を持っている私は不安であり、アフラック/給与サポート保険に加入しました。加入時は特別難しい手続きはなく電話対応の方も親切に進めていただいたので良かったです。アフラックに他の保険も加入していて特に他の保険会社と比べたと言うことはありませんが、総合的に言うとアフラック/給与サポート保険にしてまんぞくしています。

三井住友海上あいおい生命/&LIFE こども保険
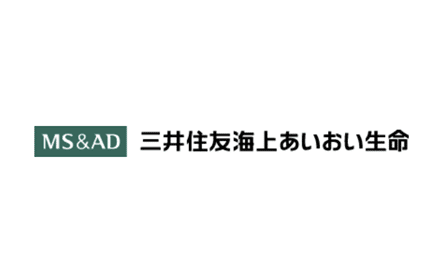
-
- 保険料の安さ
- 4
-
- 返戻率の多さ
- 2
-
- 選択肢の多さ
- 3
-
- 特約・オプションの多さ
- 4
-
- サポートの手厚さ
- 4
三井住友海上あいおい生命/&LIFE こども保険がおすすめの理由
三井住友海上あいおい生命/&LIFE こども保険がおすすめの理由は「養育年金がでる」点です。
三井住友海上あいおい生命/&LIFE こども保険は、養育年金が出る死亡保険の特徴を持った学資保険です。また、5年ごとに積立配当金が出ます。積立配当金は、運用実績によって増減し、配当ゼロということもあるものです。
デメリットは、積立配当金がいくら出るかはわからない点です。
三井住友海上あいおい生命/&LIFE こども保険の口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:1件
死亡保障だけではなく、働けなくなった場合の保障を備えたいと思ったときにいくつかの保険会社の商品が候補にあがりましたが、喫煙割引や健康割引があったことで割安に加入できると知り加入を決めました。加入してから5年ほど経過したくらいで、怪我で長期入院が必須となってしまいました。介護や三大疾病の備えのために加入した経緯があり、怪我は対象外だと思っていましたが、条件に当てはまり素早く給付金が入ってきて大変有り難かったです。
毎月もらっていた給与が今後ももらいえるのかが非常に不安になっていたときに、この保険が使えることを知り、怪我が回復するのかは心配でしたが、お金の面では幾分か安心感があり加入していてよかったと思える保険でした。生前に自分で使うことのできる保障の必要性は強く感じ、保険会社の対応も非常に満足しています。

第一生命/こども応援団・Mickey

-
- 保険料の安さ
- 2
-
- 返戻率の多さ
- 4
-
- 選択肢の多さ
- 3
-
- 特約・オプションの多さ
- 4
-
- サポートの手厚さ
- 4
第一生命/こども応援団・Mickeyがおすすめの理由
第一生命/こども応援団・Mickeyがおすすめの理由は「保険料払込の免除保障の範囲が選べる」点です。
第一生命/こども応援団・Mickeyは、保険料払込の免除保障の範囲が、契約者の死亡、契約者の三大疾病や介護状態、免除無しで選べて、保障によって保険料や返戻率が変動します。
デメリットは、返戻率はそこまで高くない点です。
第一生命/こども応援団・Mickeyの口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:1件
2度この保険を利用しています。1度目は19歳の息子に。2度目は現在2歳半の娘にです。19歳の息子の時には、入園・小学校入学・中学校入学・高校入学・高校卒業時に分けて、各ステージに合わせた金額を受け取れる設定のものにしていましたし、その受取金のお陰で入園・入学準備は非常に助けられました。2歳半の娘にかける際には、そのシステムはなく、17歳の時に一括でいくら受け取るか、それによって掛金が変わるといったシステムになっていました。高校の授業料無償化などの影響なのでしょうけれど、授業料が無償化なだけで支度にかかるお金は変わらないと思うのですが・・・。ただ、大学に進学した場合に授業料を賄えるくらいの設定にしましたし、主人に何かがあっても安心できる内容にしたので、返戻し率が少し低めにはなりましたが納得しています。

住友生命/スミセイのこどもすくすく保険

-
- 保険料の安さ
- 5
-
- 返戻率の多さ
- 3
-
- 選択肢の多さ
- 3
-
- 特約・オプションの多さ
- 4
-
- サポートの手厚さ
- 4
住友生命/スミセイのこどもすくすく保険がおすすめの理由
住友生命/スミセイのこどもすくすく保険がおすすめの理由は「保険料が安い」点です。
住友生命/スミセイのこどもすくすく保険は、12歳で10%の学資祝金、15歳で10%の学資祝金、18歳で100%の学資祝金が受け取れる仕組みです。基本保険金額の120%が受取総額ですので、その分、返戻率は低いのですが、保険料が安く設計されています。
デメリットは、返戻率はそこまで高くない点です。
住友生命/スミセイのこどもすくすく保険の口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:2件
掛け捨てであっても安く保障を確保できる商品を探していました。保険に関する知識はさほどなかったですが、シンプルな主契約と特約でさほど悩まずに20代の頃に契約しておきました。
実際に悪性ではなかったものの、上皮内新生物と診断されてしまい、手術のみ行いその後は通院となりました。
毎月の掛け金も安かったため、それほど給付額に期待はなきったですが悪性でなくても受け取れるタイプであり、思った以上の給付で安心しました。
手軽な掛け金で安心感を買えているので満足しています。
子どもたちが生まれてからずっとこちらの学資保険できました。ジュニアNISAへの移行を悩んだこともありましたが、お祝い金として受け取りたいこともあり、結局そのままの状態です。子を持つシングル、コロナ禍の不況で貯蓄が厳しい時ですが、ここだけは削れないと思い毎月払込みを行ってきました。利率を求めるとあまりお得感はないけれど、大手の安心感は捨てきれないところではあります。
高校卒業のタイミングまでに他と投資などと併せて学費をもっと増やしていきたいと考えています。
「学資保険」おすすめ比較
| サービス名 | ニッセイ学資保険 | つみたて学資 | みらいのつばさ | 学資保険 | 5年ごと利差配当付こども保険 | &LIFE こども保険 | こども応援団・Mickey | スミセイのこどもすくすく保険 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運営会社 | 日本生命 | 明治安田生命 | フコク生命 | ソニー生命 | 東京海上日動あんしん生命 | 三井住友海上あいおい生命 | 第一生命 | 住友生命 |
| 保険料:30代男性・子0歳・受取金額:200万円 | 13,350円 | 10,814円 | 10,170円 | 12,900円 | 10,856円 | 11,210円 | 16,226円 | 8,192円 |
| 保険料:40代男性・子0歳・受取金額:200万円 | 13,520円 | 10,916円 | 12,235円 | 12,960円 | 11,696円 | 12,302円 | - | 8,192円 |
| 保険料:50代男性・子0歳・受取金額:200万円 | 46,500円 | - | 15,526円 | - | - | 14,958円 | - | - |
| 保険料試算条件補足 | 保険料払込期間:18歳、学資年金開始年齢18歳、親50歳5年 | 保険料払込期間:15歳、親50歳5年 | S(ステップ)型、保険料払込期間親30歳子17歳。親40歳子14歳、親50歳子11歳 | Ⅰ型、22歳満期、100万円、保険料払込期間10歳まで | 保険料払込期間:18歳 | 保険料払込期間:18歳 | 受取総額:300万円、MickeyC型 | 保険料払込期間:12歳 |
| 返戻率 | 104.0% | 104.7% | 104.7% | 104.9% | - | - | 102.7% | 101.7% |
| 返戻率試算条件 | 30歳、保険料払込期間:18歳、学資年金開始年齢18歳、受取総額200万円 | 30歳、保険料払込期間:10歳、受取総額200万円 | S(ステップ)型、保険料払込期間11歳、受取総額200万円 | 30歳、Ⅰ型、18歳満期、100万円、保険料払込期間10歳まで、受取総額200万円 | - | - | 受取総額:300万円、MickeyC型 | 30歳、保険料払込期間:12歳、受取総額120万円 |
| 特約 | こども祝金 | - | 兄弟割引 | 5年ごと利差配当付年金支払特約 | - | こども医療特約 | 指定代理請求特約 | こども総合医療特約 こども入院保障充実特約(09) 保険契約者代理特約・被保険者代理特約 |
| 公式 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
| 口コミ | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 |
「学資保険」でおすすめのランキング/利用した方の口コミ・評判
口コミ・評判ランキングは、口コミ件数5件以上で、総合評価順に表示しています。口コミ件数5件未満のものは、口コミ件数が多い順に表示しています。
はなさく生命/はなさく一時金の評判・口コミ
口コミ総合評価
6.1点
総合評価(10点満点)
最新口コミ 口コミ投稿数:16件
子どもが産まれて半年後に契約しました。産婦人科に置かれている雑誌で何となく目にしていて、それまでは学資保険なんて無縁で全く興味も知識もありませんでしたが、調べてみると学資保険の中でもかなり返戻率が高いことが分かり、評判もとても良く、契約内容もシンプルで分かりやすかったので、一番返戻率が高くなるように前期前納払いで契約しました。担当の方もとても感じがよく親身で、他の保険を勧められるようなこともなかったです。
お世話になっている保険会社の人のお付き合いで勧められ、加入いたしました。他にも色々な学資保険はあったとは思うのですが、自分が聞いたことがある保険会社ですし、知人にも加入している人が多かったので加入したのですが、当時は無知でよくわからなかったのですが、色々みてわかったことは、ごくごく平均点だと思います。特約も他と変わらず、特色も特に和えうわけではないので、とりあえず何かに加入したいという方にはいいと思います。
貯金がなかなか出来なくて、引き落としでコツコツと積み立てていける学資保険を選びました。家計が苦しくて保険金を支払えない月があっても、翌月に払っても大丈夫な制度もあってとても助かりました。気がついたら子どもも18才になり、進学の費用にあてることができて、ほっとしています。親が病気やけがで働けない場合も、救済措置があるのは本当に助かると思います。今の世の中、明日何があるかわからないですから、最低限の保険は掛けていたほうが良いと思います。
ソニー生命の保険に加入しております。元々インターネットの保険ということで、ネット上でほとんどのことが完結するものと思い込んでいたのですが、実際には営業の方に何度も自宅まで足を運んで頂き、丁寧にご説明をして頂きました。おかげで、不明点や疑問点、不安な点などを解消して、保険に加入することができたと思っています。また加入後も、よくありがちな、入ったら入りっぱなしということはなく、丁寧にアフターフォローもして頂いて、加入保険の状況などのご説明も頂いています。以上のことから、私は非常に満足をしています。
保障内容が充実しているため、安心して加入できます。また、保険金の運用実績が良いため、将来の教育費用を確実に賄えるという点も高く評価できます。
一方で、保険料が高いと思います。また、保険金の支払いが始まる時期が限定されているため、子供が大学に進学する前に亡くなった場合は保険金を受け取れないというデメリットもあります。
総合的に考えると、ソニー生命/学資保険は将来の教育費用に備えるための有力な商品であり、保障内容や運用実績の良さからおすすめです。ただし、保険料や支払い時期に関する制限については事前によく確認しておくことが重要です。
FWD富士生命/FWDがんベスト・ゴールドの評判・口コミ
口コミ総合評価
6.1点
総合評価(10点満点)
最新口コミ 口コミ投稿数:6件
ハーフタイプを選択して加入しているので、毎月の保険料はとにかくリーズナブルで全く負担に感じる事がないですし、それでいて精神的な疾患まで保障されるので、この対象の幅広さはとても安心感があります。また、リーズナブルなので仕方ないとは言え、掛け捨てなのはやはり気にはなりましたが、今後保険料が変わる事もずっとないですし、健康について医師の方に直接相談ができるサービスもあり、万が一働けなくなった時の備えとしては十分に満足できています。
子どもを妊娠、出産を機に学資保険等について調べ始めました。日頃お世話になっている保険屋さんに相談し、候補として挙がったのがフコク生命のみらいのつばさです。自分がネットで調べた際にも口コミ等で評価を知っておりましたので安心でした。主人が特定の生命保険に加入していないことと、返戻率でこちらを選択し、払い戻しの期間はまだまだ先ですが現状不満はありません。選択肢やオプション等が充実しているとは感じませんが、保険料については満足しています。大きな企業ですので、サポートに関しては充実しています。
積み立てていく保険ですが、払込期間が10年になっており、早めに払い込みを終えるので返礼率が少し高くなります。兄弟がいるので、早めに払い込みを終えたいと思い選びました。わが家では祝い金を受け取れるタイプにしています。大学受験で一番お金が必要になりますが、中学入学や高校入学時にはまとまったお金が必要になります。子供の学用品を揃えるのに使えるので助かります。他に準備はしていないのでとても頼りにしています。
対応して説明してくださる方がとても丁寧だったので、学資保険に入りました。夫が急死したり事故に合ったりしたときなどの、いざという時には役に立つかもしれないとおもいました。何事もなければ貯金にもなります。子どもが18歳になり満期を迎え、300万円の支払いがありました。子どもが丁度大学受験の時だったので、受験料、交通費、宿泊費、入学金、授業料、マンションの入居費、新生活ための色々な物品購入のために、本当に役に立ちました。学資保険に入っていて良かったと思いました。毎月の支払金額は多くはありませんが、18年間積み立てることで大きな金額になっていてびっくりしました。
私は子どもが生まれて半年ほどでフコク生命の学資保険に加入しました。誰かに勧められたわけではなくて自分でどの学資保険がいいか調べたうえでフコク生命にしました。その当時たくさんある学資保険の中で年払いにすると返戻率が良かったことや契約者(親)にもしものことがあった時に保障は継続するけど保険料の払い込みは免除になる特約がついていたのが一番の決め手になりました。また大きい会社なので安心感や信頼感もあり加入して本当に良かったと思います。
チューリッヒ生命/終身ガン治療保険プレミアムZの評判・口コミ
口コミ総合評価
7.2点
総合評価(10点満点)
最新口コミ 口コミ投稿数:8件
私は、明治安田生命の「つみたて学資」を利用した学資保険に加入しています。この学資保険には、毎月少額の保険料を支払い、将来的な教育費を貯めることができる仕組みがあります。
利用していて良かった点は、まず、保険料が毎月の支払い額が少額であることです。これにより、教育費の負担が大きくなりすぎず、家計を圧迫することがなくなりました。
また、学資保険の選択肢が多く、自分に合ったプランを選べる点も魅力的でした。さらに、学資保険の契約期間が長く、将来的な教育費の負担を少なくすることができる点も大きなメリットです。
一方、悪かった点としては、保険金が払い戻されるまでに契約期間が必要なことがあります。また、保険料を長期間払い続ける必要があるため、収入が不安定な場合は支払いが困難になることがあります。
総じて、明治安田生命の「つみたて学資」は、将来の教育費を負担せずに貯めることができる学資保険であり、毎月少額の支払いで教育費の負担を軽減することができます。ただし、長期的な視点で契約することが必要であり、自分に合ったプランを選択することが重要です。
チューリッヒ生命のがん保険加入前に利用していたがん保険と比べてみると保証ないようがほとんど変わらないのに保険料が2割程安く年間の掛け金に結構さ差額があったので変えて良かったです。また、加入時は、電話で案内をお願いするとすぐに対応してくれ資料などすぐに送ってくださいました。また、電話対応もすごくよく的確に説明してくれ、説明内容も分かりやすかったです。保険内容も、もしがんになった時でもこの保険である程度は対応でき家族思いの保険だなと感じました。
上の世代の身内が皆ガンになっているので、ガン保険は必須だと思っています。何年も払っていて、まだ一度も申請したことはないですが、安心を得るため、かなり手厚いものにしています。いくつも比較して、値段の割に手厚いものを選んだのがチューリッヒの保険です。最近は、入院が必要でないことも多いみたいなので、通院治療の費用のでるものを選びました。実際、最近、身内がガンの治療のため毎日通院が必要になったので、やはり通院ででる保険にしていてよかったなと感じています。
保険金額の選択肢が広く、いろいろな状況をあわせて設定できるのが助かる。また、保険医金の支払いがはやく、就業不能状態でお金をかせげなくなった時に非常に助けていただいた。またネットで手続きを完了させられるところも、まともに動けない状態になっていた時は非常に助かる。このような上質なサービスが、他者と比較して安く受けられる点が、中流層には嬉しい。担当者によりけりかもしれないが、私の時は物腰のよい人で、不快な思いをすることなく話を勧められた。
子供が生まれると同時に学資保険に入りました。子供が生まれたら、すぐ入るのが親の務めだよと両親に口酸っぱく言われたことを思い出します。子供本人が中学三年生になるまでに、300万円程度貯めるタイプの学資保険に入りました。友人の母親が、明治安田生命に勤めていたので、その縁で入りました。月々の払い込みが自動的に行われるので、そのお金は元々ないものとして毎日の生活を計画的に過ごしていました。子供の進学時のお金に困るということだけは避けることができました。子供が生まれたら、すぐに学資保険加入!!大切な合言葉です。
アクサダイレクト生命/がん終身の評判・口コミ
口コミ総合評価
5.6点
総合評価(10点満点)
最新口コミ 口コミ投稿数:5件
アクサダイレクト生命がん保険について、良い点が2点あります。1点目は、毎月の拠出額が手頃で若い年齢層でも入ることができる点です。毎月1650円で入院給付金が10000円、がんと診断されたら100万円もらえます。家計に負担をかけず万が一に備えることができます。2点目は、サービスが充実している点です。子供が熱を出した際、24時間電話健康相談サービスを利用しました。すぐに病院を紹介してもらいとても助かりました。
子供達がまだ小さい30代前半頃、今後の教育費や自分が病気になった際に掛かる費用が心配になりました。保険の見直し相談で、病気で怖いのは癌であること、若いうちの加入が望ましいことを説明され、「がん保険」を勧められました。家系的にも心配な部分もあり、加入することを前提に考え、数社見積もりを取って、値段と保障内容において納得できるアクサに決めました。一番の決め手は値段です。色々と調べましたが、がん保険は値段の高いものが多く、支払いにおいて無理のないものを選びました。終身であるため万が一の時も慌てずに対応出来ると思っております。
貯金をそのまま持っていてもという事で色々とすすめられて日本生命に一括納付で契約致しました。学資保険は何処もあまりリターンがないのでこんなものなのかなと思っております。スマイルポイントの還元率もこんなものかなと思っております。たまに違う保険を勧誘されたり、担当の方が毎年変わるなど、メールも沢山きたりするのが嫌だなとは思っております。担当の方が派手なギャルっぽい人や若い人など、年々不安にはなったりしております。
今小学生の子供がいますが大学に行かせてあげたいと夫婦で話し合い、学資保険に申し込むことにしました。初めての契約なので不安はありましたが手続きは複雑なことはなく電話等でスムーズに手続きを進めることができ、対応してくれた人もとても親切に対応してくれたので良かったです。
契約後も契約の情報等もウェブ上で簡単に確認することができるのでいいなと思いました。今回は日本生命で契約しましたがもしまた新規で契約する場面があれば他の保険会社とも比較して決めていきたいと思います。
日本生命の学資保険を利用しました。子供が大学受験前に受け取れるように年齢設定もできるし、子供が産まれてすぐに加入しておけばお祝い金もつけられるので、とてもありがたかったです。このお祝い金が何年か置きに貰えるので、小学校入学や中学入学の時も入学準備の足しになったので凄く助かりました。返戻率も当時、他の保険会社に比べて良かったので利用しました。ただ保険料は少し高いかな…と感じました。子供が大学受験する際には凄く役に立ちましたが今後、孫が産まれたら保険料を考えると、どうしようか迷う所ではあります。
ライフネット生命/ダブルエールの評判・口コミ
口コミ総合評価
3.8点
総合評価(10点満点)
最新口コミ 口コミ投稿数:1件
2度この保険を利用しています。1度目は19歳の息子に。2度目は現在2歳半の娘にです。19歳の息子の時には、入園・小学校入学・中学校入学・高校入学・高校卒業時に分けて、各ステージに合わせた金額を受け取れる設定のものにしていましたし、その受取金のお陰で入園・入学準備は非常に助けられました。2歳半の娘にかける際には、そのシステムはなく、17歳の時に一括でいくら受け取るか、それによって掛金が変わるといったシステムになっていました。高校の授業料無償化などの影響なのでしょうけれど、授業料が無償化なだけで支度にかかるお金は変わらないと思うのですが・・・。ただ、大学に進学した場合に授業料を賄えるくらいの設定にしましたし、主人に何かがあっても安心できる内容にしたので、返戻し率が少し低めにはなりましたが納得しています。
オリックス生命/がん保険Believe[ビリーブ]の評判・口コミ
口コミ総合評価
4.2点
総合評価(10点満点)
最新口コミ 口コミ投稿数:2件
掛け捨てであっても安く保障を確保できる商品を探していました。保険に関する知識はさほどなかったですが、シンプルな主契約と特約でさほど悩まずに20代の頃に契約しておきました。
実際に悪性ではなかったものの、上皮内新生物と診断されてしまい、手術のみ行いその後は通院となりました。
毎月の掛け金も安かったため、それほど給付額に期待はなきったですが悪性でなくても受け取れるタイプであり、思った以上の給付で安心しました。
手軽な掛け金で安心感を買えているので満足しています。
子どもたちが生まれてからずっとこちらの学資保険できました。ジュニアNISAへの移行を悩んだこともありましたが、お祝い金として受け取りたいこともあり、結局そのままの状態です。子を持つシングル、コロナ禍の不況で貯蓄が厳しい時ですが、ここだけは削れないと思い毎月払込みを行ってきました。利率を求めるとあまりお得感はないけれど、大手の安心感は捨てきれないところではあります。
高校卒業のタイミングまでに他と投資などと併せて学費をもっと増やしていきたいと考えています。
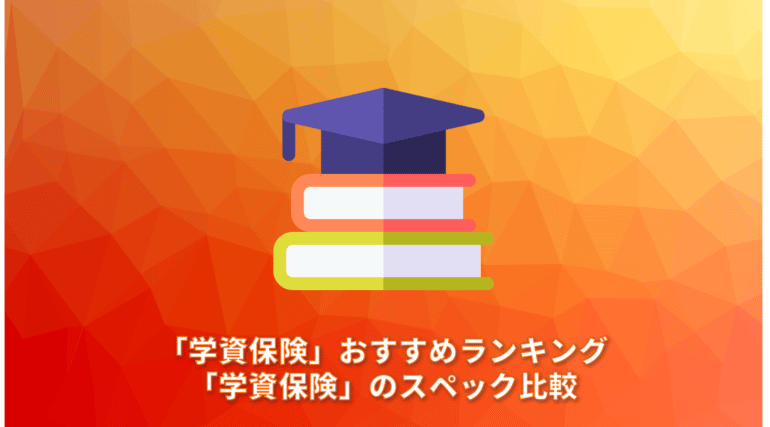



最新口コミ 口コミ投稿数:5件
アクサダイレクト生命がん保険について、良い点が2点あります。1点目は、毎月の拠出額が手頃で若い年齢層でも入ることができる点です。毎月1650円で入院給付金が10000円、がんと診断されたら100万円もらえます。家計に負担をかけず万が一に備えることができます。2点目は、サービスが充実している点です。子供が熱を出した際、24時間電話健康相談サービスを利用しました。すぐに病院を紹介してもらいとても助かりました。
子供達がまだ小さい30代前半頃、今後の教育費や自分が病気になった際に掛かる費用が心配になりました。保険の見直し相談で、病気で怖いのは癌であること、若いうちの加入が望ましいことを説明され、「がん保険」を勧められました。家系的にも心配な部分もあり、加入することを前提に考え、数社見積もりを取って、値段と保障内容において納得できるアクサに決めました。一番の決め手は値段です。色々と調べましたが、がん保険は値段の高いものが多く、支払いにおいて無理のないものを選びました。終身であるため万が一の時も慌てずに対応出来ると思っております。
貯金をそのまま持っていてもという事で色々とすすめられて日本生命に一括納付で契約致しました。学資保険は何処もあまりリターンがないのでこんなものなのかなと思っております。スマイルポイントの還元率もこんなものかなと思っております。たまに違う保険を勧誘されたり、担当の方が毎年変わるなど、メールも沢山きたりするのが嫌だなとは思っております。担当の方が派手なギャルっぽい人や若い人など、年々不安にはなったりしております。
今小学生の子供がいますが大学に行かせてあげたいと夫婦で話し合い、学資保険に申し込むことにしました。初めての契約なので不安はありましたが手続きは複雑なことはなく電話等でスムーズに手続きを進めることができ、対応してくれた人もとても親切に対応してくれたので良かったです。
契約後も契約の情報等もウェブ上で簡単に確認することができるのでいいなと思いました。今回は日本生命で契約しましたがもしまた新規で契約する場面があれば他の保険会社とも比較して決めていきたいと思います。
日本生命の学資保険を利用しました。子供が大学受験前に受け取れるように年齢設定もできるし、子供が産まれてすぐに加入しておけばお祝い金もつけられるので、とてもありがたかったです。このお祝い金が何年か置きに貰えるので、小学校入学や中学入学の時も入学準備の足しになったので凄く助かりました。返戻率も当時、他の保険会社に比べて良かったので利用しました。ただ保険料は少し高いかな…と感じました。子供が大学受験する際には凄く役に立ちましたが今後、孫が産まれたら保険料を考えると、どうしようか迷う所ではあります。